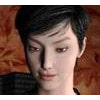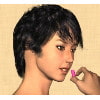スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
奪われた妻と俺の性11
「ほら、ここも汚れてるでしょ。もっと舌を出して舐め取りなさいよ。」
愛莉の声が頭上から響く。
「は、はいっ・・・・」
正治は情けない声で返事をしながら履き古されたそのローファーを必死に舐め続けるしかなかった。
「まったく、お隣にこんな変態さんが住んでるとは思わなかったわ。」
愛莉は靴の底を正治の顔に押しつけながら呟く。若いから順応も早い。すっかり彼女はサディストの属性に目覚めた様だった。
「そーねー、セーラー服姿で娘さんの靴を犬みたいに舐めさせられてるなんて、ご家族には見せられないわよねぇ・・・・あっ!ここに奥さんがいたっけ?きゃははははっ!」
結衣の笑い声に未穂が少しだけ顔を赤らめた。
「ねぇ、お隣のおばさん。あなたはこんな情けない旦那でもいいんですかぁ?」
愛莉は未穂にまでぞんざいな口調で聞いた。
「はっ・・・はいっ・・・・」
さすがに奴隷の立場をわきまえている未穂は、年下の少女に向かっても丁寧に答えた。
「あ、あの・・・もうあたしは・・・・こいつのものではありません・・・・。わ、私は身も心も・・・こちらの、恭平様に捧げておりますので・・・。
「なにそれ?浮気ってこと?」
未穂の言葉はさすがに年端もいかない愛莉には理解出来ない様だった。
「浮気じゃないさ。」
恭平がほくそ笑んで答える。
「未穂はほんの少しだけその包茎短小野郎に騙されてただけだよ。それに俺みたいに魅力的な男はこうやって何人も女を持っていて当然なんだよ。愛莉ちゃんもどう?悪い様にはしないぜ。」
愛莉のいやだという答えに恭平は苦笑いした。
「まあとにかく、今のこいつらは俺と結衣の奴隷ってことだ。」
「ど・れ・い・・・・」
愛莉が不思議そうに呟いた。
「ほら、そろそろ行くわよ!」
結衣がまだ四つん這いで廊下に伏せている正治を立たせる。
「じゃあな愛莉ちゃん。またこいつらを好きな様に使ってくれていいからな。」
バイバイと手を振る愛莉に別れを告げ、こうして二人の奴隷は夜の街に連れ出されてしまった。
「ねぇ・・・見て・・・・」
「なにかの撮影かしら・・・・」
道行く人がひそひそと話しながら二人の傍をそそくさと離れていく。
「うわっ!変態!」
「いやだあぁっ・・きもいぃっ!!」
なかにはそんな言葉を吐き捨てる様に二人に投げかける女子中高生までもがいた。だがそれも当たり前だ。まだ若くて美しい未穂はともかく、正治の方はいくら女顔といえども女子幸生にはとうてい見えない。そんな二人が超ミニスカのセーラー服で腕を組んで歩かされているのだから嫌でも人の目に止まってしまう。
「み、未穂・・・お前・・恥ずかしくないのか・・・」
正治は小声で悲鳴を上げた。日頃恭平の調教に慣れている未穂と違って彼は女装での外出など初めてだから無理も無かった。
「だって私は奴隷ですもの。これが恭平様の命令だとしたら私は耐えるしかないの。」
正治は妻が本当に心からあの憎い男に陶酔している事を知り心穏やかではなくなった。だが今の彼はそんな事を考えている余裕は無かった。
「ほら、もっと仲良しそうに歩きなさいってご主人様がおっしゃったでしょ!」
未穂に言われ、正治はピタリと未穂の体に身を寄せる。
だがその瞬間、着せられているセーラー服の袖とスカートが触れあい、繁華街を吹き抜ける夜風が二人のスカートをそっと捲り上げた。
「うわぁっ!」
正治は思わず男性の様に悲鳴を上げてしまった。たちどころに聞こえる辺りからの声。
「やっぱり、男だったんだ・・・」
「見た?パンツまで女物だったよ・・・・」
「うんうん、しっかも子供みたいに名前まで書いてあったよ。」
「えぇっ!へんたーい!!」
しっかりと恥ずかしい下着を見られてしまった事を知り、意気消沈する正治だったが、その頬に妻の張り手が飛んだ。
「いてぇっ!!・・・何をするんだよ・・・未穂・・・」
未穂は怯える正治に言い放った。
「男みたいな声を出しておいて、何がじゃないでしょ?私はあなたを女らしく躾ける様に恭平様達に命じられてるんだからね。今度そんな風に悲鳴を上げたら許さないわよ!」
「は、はいっ・・・・」
未穂のあまりの剣幕に人目も気にせず正治はそう返事した。
「本当に分かったの?」
驚くべき事に、未穂はそう言って衆人環視の中、正治のスカートを捲り上げた。
「うっ・・・・」
叫ぼうとして、正治は思いとどまる。
「きゃ・・・きゃっ・・・」
「もっと大きな声で!」
正治はやぶれかぶれで叫んだ。
「きゃ・・・きゃ!・・・・きゃぁぁっ!!」
気が付けば後ろに恭平と結衣が苦笑しながら立っていた。
「あはは、いいわよ。、本当に痴漢にあった女子高生みたいよ。」
「やればできるじゃないか。お前、本当はこんな風にされたかったんじゃねぇの?・・・未穂、もっと厳しく躾けてやるんだぞ。」
「はい、ご主人様。」
文句の一つを言う事も出来ず、正治はスカートの裾を気にしながら、皆の軽蔑の眼差しを受け、夜の街をとぼとぼと歩くしかなかった。
愛莉の声が頭上から響く。
「は、はいっ・・・・」
正治は情けない声で返事をしながら履き古されたそのローファーを必死に舐め続けるしかなかった。
「まったく、お隣にこんな変態さんが住んでるとは思わなかったわ。」
愛莉は靴の底を正治の顔に押しつけながら呟く。若いから順応も早い。すっかり彼女はサディストの属性に目覚めた様だった。
「そーねー、セーラー服姿で娘さんの靴を犬みたいに舐めさせられてるなんて、ご家族には見せられないわよねぇ・・・・あっ!ここに奥さんがいたっけ?きゃははははっ!」
結衣の笑い声に未穂が少しだけ顔を赤らめた。
「ねぇ、お隣のおばさん。あなたはこんな情けない旦那でもいいんですかぁ?」
愛莉は未穂にまでぞんざいな口調で聞いた。
「はっ・・・はいっ・・・・」
さすがに奴隷の立場をわきまえている未穂は、年下の少女に向かっても丁寧に答えた。
「あ、あの・・・もうあたしは・・・・こいつのものではありません・・・・。わ、私は身も心も・・・こちらの、恭平様に捧げておりますので・・・。
「なにそれ?浮気ってこと?」
未穂の言葉はさすがに年端もいかない愛莉には理解出来ない様だった。
「浮気じゃないさ。」
恭平がほくそ笑んで答える。
「未穂はほんの少しだけその包茎短小野郎に騙されてただけだよ。それに俺みたいに魅力的な男はこうやって何人も女を持っていて当然なんだよ。愛莉ちゃんもどう?悪い様にはしないぜ。」
愛莉のいやだという答えに恭平は苦笑いした。
「まあとにかく、今のこいつらは俺と結衣の奴隷ってことだ。」
「ど・れ・い・・・・」
愛莉が不思議そうに呟いた。
「ほら、そろそろ行くわよ!」
結衣がまだ四つん這いで廊下に伏せている正治を立たせる。
「じゃあな愛莉ちゃん。またこいつらを好きな様に使ってくれていいからな。」
バイバイと手を振る愛莉に別れを告げ、こうして二人の奴隷は夜の街に連れ出されてしまった。
「ねぇ・・・見て・・・・」
「なにかの撮影かしら・・・・」
道行く人がひそひそと話しながら二人の傍をそそくさと離れていく。
「うわっ!変態!」
「いやだあぁっ・・きもいぃっ!!」
なかにはそんな言葉を吐き捨てる様に二人に投げかける女子中高生までもがいた。だがそれも当たり前だ。まだ若くて美しい未穂はともかく、正治の方はいくら女顔といえども女子幸生にはとうてい見えない。そんな二人が超ミニスカのセーラー服で腕を組んで歩かされているのだから嫌でも人の目に止まってしまう。
「み、未穂・・・お前・・恥ずかしくないのか・・・」
正治は小声で悲鳴を上げた。日頃恭平の調教に慣れている未穂と違って彼は女装での外出など初めてだから無理も無かった。
「だって私は奴隷ですもの。これが恭平様の命令だとしたら私は耐えるしかないの。」
正治は妻が本当に心からあの憎い男に陶酔している事を知り心穏やかではなくなった。だが今の彼はそんな事を考えている余裕は無かった。
「ほら、もっと仲良しそうに歩きなさいってご主人様がおっしゃったでしょ!」
未穂に言われ、正治はピタリと未穂の体に身を寄せる。
だがその瞬間、着せられているセーラー服の袖とスカートが触れあい、繁華街を吹き抜ける夜風が二人のスカートをそっと捲り上げた。
「うわぁっ!」
正治は思わず男性の様に悲鳴を上げてしまった。たちどころに聞こえる辺りからの声。
「やっぱり、男だったんだ・・・」
「見た?パンツまで女物だったよ・・・・」
「うんうん、しっかも子供みたいに名前まで書いてあったよ。」
「えぇっ!へんたーい!!」
しっかりと恥ずかしい下着を見られてしまった事を知り、意気消沈する正治だったが、その頬に妻の張り手が飛んだ。
「いてぇっ!!・・・何をするんだよ・・・未穂・・・」
未穂は怯える正治に言い放った。
「男みたいな声を出しておいて、何がじゃないでしょ?私はあなたを女らしく躾ける様に恭平様達に命じられてるんだからね。今度そんな風に悲鳴を上げたら許さないわよ!」
「は、はいっ・・・・」
未穂のあまりの剣幕に人目も気にせず正治はそう返事した。
「本当に分かったの?」
驚くべき事に、未穂はそう言って衆人環視の中、正治のスカートを捲り上げた。
「うっ・・・・」
叫ぼうとして、正治は思いとどまる。
「きゃ・・・きゃっ・・・」
「もっと大きな声で!」
正治はやぶれかぶれで叫んだ。
「きゃ・・・きゃ!・・・・きゃぁぁっ!!」
気が付けば後ろに恭平と結衣が苦笑しながら立っていた。
「あはは、いいわよ。、本当に痴漢にあった女子高生みたいよ。」
「やればできるじゃないか。お前、本当はこんな風にされたかったんじゃねぇの?・・・未穂、もっと厳しく躾けてやるんだぞ。」
「はい、ご主人様。」
文句の一つを言う事も出来ず、正治はスカートの裾を気にしながら、皆の軽蔑の眼差しを受け、夜の街をとぼとぼと歩くしかなかった。
奪われた妻と俺の性10
「あ、愛莉ちゃん・・・・」
それは正治の隣の部屋に住む木下という家庭の長女である娘だった。もちろんお互いに顔見知りである。
「あ、あの・・・・その・・・姿・・・は・・・」
彼女は驚きを通り越して驚愕と怯えの入り混じった表情で正治を注視している。正治はまるで人生が終わってしまったかの様な思いを感じた。
「こ、これはっ・・・」
正治はうまい言い訳を考えるがどうにも繕いようがなかった。罰ゲームというにはその制服は立派すぎたし(なにしろ本物であるのだ)、未穂の方は普段とは全く異なる露出の多い服を着せられている。そしてなにより彼には作り笑いを浮かべる余裕さえ無かったのだ。
「あら、近所のお嬢さんかしら?」
沈黙の中声を出したのは結衣だった。
「は、はい・・・隣のものです・・・。」
愛莉は訝しげに答える。
「そう、気の毒ね。お隣にこんなヘンタイが住んでいるなんて。」
結衣は正治のセーラー服のリボンをいじりながらそう言って笑った。
「えっ?」
真面目な愛莉には女装趣味の男性の存在など想像も出来ないのだろう。彼女は驚いて再び正治の顔を見る。
「ほら、告白しなさいよ。私は女装趣味の変態です。いままで普通のサラリーマンの振りをして申し訳ありませんでしたってね。」
「や、やめ・・・・」
結衣の言葉に正治は精一杯抗うが、サディストの彼女がそんな事で怯むはずも無い。
「ごめんなさいね、こいつ前からお隣の女子高生と同じ制服が着たいって言ってたのよ。それで着るだけじゃ不満でどうしても外出したいていってきかないから、こうやって仕方無くみんなで出掛けようとしてたの。男の癖に、しかもいい歳してセーラー服だなんて気持悪いわよねぇ。」
「い、いえ・・・・その・・・」
愛莉は否定するが、その瞳には既に蔑みの成分が含まれていた。
「ふ、服装なんて・・・じ、自由ですし・・・・」
「ふーん。お嬢ちゃん優しいのねえ。じゃあ、これはどうかしら?」
「ぃやぁぁぁぁっ!!」
不意に結衣にスカートを捲り上げられ、正治は悲鳴を漏らした。静かな夕暮れのマンションの廊下に彼の声が響き渡る。
「あ・・あ・・・あっ・・・やめっ・・・・」
必死に逃げ出そうとする正治だったが、恭平に腕をつかまれてそれも出来ない。彼の恥ずかしいショーツは今や愛莉に丸見えとなってしまっていた。
「やだぁっ・・・・」
さすがの愛莉ももう驚きではなく、完全に侮蔑の表情で正治をみやる。
「もりかわ・・・ま・・の・・・ん?」
ゆっくりと正治のショーツに書かれた名前を読み取ると、愛莉は不思議そうに結衣を見つめた。結衣は頷いて説明する。
「そうよ、この子は正治じゃなくって『マノン』ちゃんなの。セーラー服着て『正治』じゃ変でしょ?」
愛莉は少し考えてから笑って言った。
「んふふ。まるで犬みたいです。」
「でしょ。あたしが前に飼ってた犬の名前を継がせてあげたの。ほらっマノン、お隣のご主人様にご挨拶なさい。」
「そっ・・・そんなっ・・・・」
いくらなんでも隣の娘に向かってそんな事ができる筈もない。躊躇う正治だったが、そんな彼の我が儘が許される筈も無かった。
「まだつまらんプライドが残ってるみたいだな。未穂!」
「はい、ご主人様。」
「み、未穂さんっ・・・」
未穂の言葉に愛莉は驚く。彼女にとって未穂は憧れの美人のお姉さんだったのだ。しかし未穂のとった行動はそのセリフ以上に恐るべきものだった。
「ィイヤァァァァァッーーーーーー!!」
再び正治の絶叫がこだまする。未穂は彼のショーツを膝までずり下ろしてしまったのだった。
「きゃっ!」
愛莉は短く悲鳴をあげると両手で顔を塞いだ。
「み、みないでっ!みないでぇっ!!」
この歳になるまでひた隠しにしてきた包茎短小のペニスをまだ幼い少女に見られる屈辱に正治はもがき苦しむ。
「ほらっ、きちんと見てあげなさい。この子は犬だから平気でしょ?」
結衣にそう促され愛莉は戸惑いながらも少しづつ薄目を開け始めた。
「ーーーーゃーっ!・・・・」
涙を溢さないばかりに正治は足を震わせながら小さな悲鳴を漏らす。しかし愛莉は大胆にもその部分に顔を近づけて、あろうことか笑い出した。
「ぷっ!・・・・・きゃはははははっ!!」
「あ、愛莉ちゃん・・・・」
てっきり悲鳴を上げて逃げ出され、場合によっては露出魔として訴えられるかとまで思っていた正治は驚いた。
「な、なに、このおちんちん。どうしてまだ皮被ってるの?」
お腹を押さえながら、誰にでもなく愛莉は尋ねる。
「それはねお嬢ちゃん。包茎っていうのよ。」
「ホーケー?」
結衣に向かって愛莉が首を傾げる。
「でも大人になれば剥けるんでしょ。私の弟の・・・小学生の弟だってもう剥けてますよ。それに・・・」
もう一度愛莉はチラリと正治のペニスを見てプッと吹き出す。
「それに、どうしてこんなに小さいんですか?これじゃー弟の三分の一くらいしかないですよ。」
「あははは、あんたのチンコ小学生以下だってさ。あはははは!」
結衣が大笑いしながら正治の背中を叩く。
「おい、マノン。お隣のお嬢様がお聞きされてるんだ。きちんと答えるのが愛犬の義務だろう。教えてやるからこう答えて・・・・」
恭平は正治に耳打ちした。
「そ、そんな・・・・」
「言えないならこのままお嬢さんのお家に上がり込むか?それで弟さんのペニスを見せてもらえばいいさ。」
「い!言いますっ!」
恭平ならやりかねない。覚悟を決めた正治がゆっくりと口を動かし始めた。
「そ、その・・・あ、あたしは・・・お、女の子のせ、制服を・・・着るのが・・・好きな・・・ヘンタイ男です・・から・・・お、オチンチン・・なんて・・・・必要ないんです・・・。」
愛莉はほくそ笑みながらその言葉を聞いている。もう彼女が完全に正治をペット以下にしか思っていないのは明白だった。
「だ、だから・・・・あ、あたしの汚い包茎チンチンをご覧下さいませ、ご主人様ぁ!」
正治は恭平に言われた通りそう言うと、自らの手でスカートの裾を持ち上げ、足をがに股に開いて舌出すと、はぁはぁと言いながら膝を震わせる。それは犬のチンチンの姿勢に違い無かった。
「そう。偉いワンちゃんね。」
愛莉は納得した様に呟くと、まるで本当に愛犬にする様に正治の頭を撫でた。
「でもね。犬の分際でご主人様と同じ制服が着たいなんてとんでもないわね・・・・」
彼女はそう言うと、ローファーを履いた右足を後方の宙に向かって大きく振りかぶる。
「気持悪いのよ、このヘンタイ牝犬っ!!」
大きく開いた股の間を愛莉の白く美しい足首が通過し、次の瞬間正治の剥き出しの性器を激しくローファーの甲が打ち付ける。同時に正治は彼女が学校で女子空手部の主将を務めていると聞いた事を思い出していた。
「・・・・んっ・・・・・んうっぐぅぅゎぁぁっ!!!!!」
強かに睾丸とペニスを打ち付けられ、そのショックに小便と精液とカウパーの入り混じった混濁液が正治のペニスからほとばしる。声も出ないほどの激痛の中、正治はその場に膝をついて前のめりに倒れ込んだ。
「汚いっ!!靴が汚れちゃったわ・・・舐め取って綺麗にしてよ。」
その正治の前に愛莉が靴先を差し出す。その先には彼が出してしまった汚らしい液が糸を引いてこびり付いていた。
「はっ、はい、ご主人様っ・・・」
もう正治に刃向かう気力は無かった。彼は股間の激痛に耐えながら汚れた愛莉の靴先を一心不乱に舐め始めた。
それは正治の隣の部屋に住む木下という家庭の長女である娘だった。もちろんお互いに顔見知りである。
「あ、あの・・・・その・・・姿・・・は・・・」
彼女は驚きを通り越して驚愕と怯えの入り混じった表情で正治を注視している。正治はまるで人生が終わってしまったかの様な思いを感じた。
「こ、これはっ・・・」
正治はうまい言い訳を考えるがどうにも繕いようがなかった。罰ゲームというにはその制服は立派すぎたし(なにしろ本物であるのだ)、未穂の方は普段とは全く異なる露出の多い服を着せられている。そしてなにより彼には作り笑いを浮かべる余裕さえ無かったのだ。
「あら、近所のお嬢さんかしら?」
沈黙の中声を出したのは結衣だった。
「は、はい・・・隣のものです・・・。」
愛莉は訝しげに答える。
「そう、気の毒ね。お隣にこんなヘンタイが住んでいるなんて。」
結衣は正治のセーラー服のリボンをいじりながらそう言って笑った。
「えっ?」
真面目な愛莉には女装趣味の男性の存在など想像も出来ないのだろう。彼女は驚いて再び正治の顔を見る。
「ほら、告白しなさいよ。私は女装趣味の変態です。いままで普通のサラリーマンの振りをして申し訳ありませんでしたってね。」
「や、やめ・・・・」
結衣の言葉に正治は精一杯抗うが、サディストの彼女がそんな事で怯むはずも無い。
「ごめんなさいね、こいつ前からお隣の女子高生と同じ制服が着たいって言ってたのよ。それで着るだけじゃ不満でどうしても外出したいていってきかないから、こうやって仕方無くみんなで出掛けようとしてたの。男の癖に、しかもいい歳してセーラー服だなんて気持悪いわよねぇ。」
「い、いえ・・・・その・・・」
愛莉は否定するが、その瞳には既に蔑みの成分が含まれていた。
「ふ、服装なんて・・・じ、自由ですし・・・・」
「ふーん。お嬢ちゃん優しいのねえ。じゃあ、これはどうかしら?」
「ぃやぁぁぁぁっ!!」
不意に結衣にスカートを捲り上げられ、正治は悲鳴を漏らした。静かな夕暮れのマンションの廊下に彼の声が響き渡る。
「あ・・あ・・・あっ・・・やめっ・・・・」
必死に逃げ出そうとする正治だったが、恭平に腕をつかまれてそれも出来ない。彼の恥ずかしいショーツは今や愛莉に丸見えとなってしまっていた。
「やだぁっ・・・・」
さすがの愛莉ももう驚きではなく、完全に侮蔑の表情で正治をみやる。
「もりかわ・・・ま・・の・・・ん?」
ゆっくりと正治のショーツに書かれた名前を読み取ると、愛莉は不思議そうに結衣を見つめた。結衣は頷いて説明する。
「そうよ、この子は正治じゃなくって『マノン』ちゃんなの。セーラー服着て『正治』じゃ変でしょ?」
愛莉は少し考えてから笑って言った。
「んふふ。まるで犬みたいです。」
「でしょ。あたしが前に飼ってた犬の名前を継がせてあげたの。ほらっマノン、お隣のご主人様にご挨拶なさい。」
「そっ・・・そんなっ・・・・」
いくらなんでも隣の娘に向かってそんな事ができる筈もない。躊躇う正治だったが、そんな彼の我が儘が許される筈も無かった。
「まだつまらんプライドが残ってるみたいだな。未穂!」
「はい、ご主人様。」
「み、未穂さんっ・・・」
未穂の言葉に愛莉は驚く。彼女にとって未穂は憧れの美人のお姉さんだったのだ。しかし未穂のとった行動はそのセリフ以上に恐るべきものだった。
「ィイヤァァァァァッーーーーーー!!」
再び正治の絶叫がこだまする。未穂は彼のショーツを膝までずり下ろしてしまったのだった。
「きゃっ!」
愛莉は短く悲鳴をあげると両手で顔を塞いだ。
「み、みないでっ!みないでぇっ!!」
この歳になるまでひた隠しにしてきた包茎短小のペニスをまだ幼い少女に見られる屈辱に正治はもがき苦しむ。
「ほらっ、きちんと見てあげなさい。この子は犬だから平気でしょ?」
結衣にそう促され愛莉は戸惑いながらも少しづつ薄目を開け始めた。
「ーーーーゃーっ!・・・・」
涙を溢さないばかりに正治は足を震わせながら小さな悲鳴を漏らす。しかし愛莉は大胆にもその部分に顔を近づけて、あろうことか笑い出した。
「ぷっ!・・・・・きゃはははははっ!!」
「あ、愛莉ちゃん・・・・」
てっきり悲鳴を上げて逃げ出され、場合によっては露出魔として訴えられるかとまで思っていた正治は驚いた。
「な、なに、このおちんちん。どうしてまだ皮被ってるの?」
お腹を押さえながら、誰にでもなく愛莉は尋ねる。
「それはねお嬢ちゃん。包茎っていうのよ。」
「ホーケー?」
結衣に向かって愛莉が首を傾げる。
「でも大人になれば剥けるんでしょ。私の弟の・・・小学生の弟だってもう剥けてますよ。それに・・・」
もう一度愛莉はチラリと正治のペニスを見てプッと吹き出す。
「それに、どうしてこんなに小さいんですか?これじゃー弟の三分の一くらいしかないですよ。」
「あははは、あんたのチンコ小学生以下だってさ。あはははは!」
結衣が大笑いしながら正治の背中を叩く。
「おい、マノン。お隣のお嬢様がお聞きされてるんだ。きちんと答えるのが愛犬の義務だろう。教えてやるからこう答えて・・・・」
恭平は正治に耳打ちした。
「そ、そんな・・・・」
「言えないならこのままお嬢さんのお家に上がり込むか?それで弟さんのペニスを見せてもらえばいいさ。」
「い!言いますっ!」
恭平ならやりかねない。覚悟を決めた正治がゆっくりと口を動かし始めた。
「そ、その・・・あ、あたしは・・・お、女の子のせ、制服を・・・着るのが・・・好きな・・・ヘンタイ男です・・から・・・お、オチンチン・・なんて・・・・必要ないんです・・・。」
愛莉はほくそ笑みながらその言葉を聞いている。もう彼女が完全に正治をペット以下にしか思っていないのは明白だった。
「だ、だから・・・・あ、あたしの汚い包茎チンチンをご覧下さいませ、ご主人様ぁ!」
正治は恭平に言われた通りそう言うと、自らの手でスカートの裾を持ち上げ、足をがに股に開いて舌出すと、はぁはぁと言いながら膝を震わせる。それは犬のチンチンの姿勢に違い無かった。
「そう。偉いワンちゃんね。」
愛莉は納得した様に呟くと、まるで本当に愛犬にする様に正治の頭を撫でた。
「でもね。犬の分際でご主人様と同じ制服が着たいなんてとんでもないわね・・・・」
彼女はそう言うと、ローファーを履いた右足を後方の宙に向かって大きく振りかぶる。
「気持悪いのよ、このヘンタイ牝犬っ!!」
大きく開いた股の間を愛莉の白く美しい足首が通過し、次の瞬間正治の剥き出しの性器を激しくローファーの甲が打ち付ける。同時に正治は彼女が学校で女子空手部の主将を務めていると聞いた事を思い出していた。
「・・・・んっ・・・・・んうっぐぅぅゎぁぁっ!!!!!」
強かに睾丸とペニスを打ち付けられ、そのショックに小便と精液とカウパーの入り混じった混濁液が正治のペニスからほとばしる。声も出ないほどの激痛の中、正治はその場に膝をついて前のめりに倒れ込んだ。
「汚いっ!!靴が汚れちゃったわ・・・舐め取って綺麗にしてよ。」
その正治の前に愛莉が靴先を差し出す。その先には彼が出してしまった汚らしい液が糸を引いてこびり付いていた。
「はっ、はい、ご主人様っ・・・」
もう正治に刃向かう気力は無かった。彼は股間の激痛に耐えながら汚れた愛莉の靴先を一心不乱に舐め始めた。
奪われた妻と俺の性09
沢山の応援コメありがとうございます。
まっことゆっくりですが続けて参りますので宜しくお願いします。
「ほらっ、さっさとこれに着替えるのよ。」
未穂から受け取った衣服を目にし、正治は今日何度目かの驚愕を味わう。
「ちょ、ちょっと待て!俺にこれを着ろっていうのか?」
妻である筈の未穂に詰め寄る正治。だが、彼女はもう正治のものでは無かった。
「先輩に無礼よ!」
躊躇無く未穂から平手打ちを頬に受け、正治は呆然となった。
「大体、いまでもこんな格好して今更何が恥ずかしいのよ。男の癖にメイド服着て、恭平様の精液と自分のお漏らしででべたべたに汚しちゃってる癖に。」
そう言われては返す言葉も無かった。
「くっ・・・・」
だがまだ少しプライドを残した正治は拳を握ってその衣装を見つめる。それは男性が着るには余りにも恥ずかしい衣装、女子学生用のセーラー服だったからだ。
「あははは、意外と似合うじゃないか。」
二人が着替え終わった姿を目にした恭平が高らかに笑う。
「ホント、制服の魔力って怖いわね。あんたも年増の癖にちゃんと女子高生に見えるわよ。」
結衣までもが未穂を揶揄するが、未穂は殊勝にも年下の小娘に向かって頭を下げていた。
「未穂、きちんと下着も穿かせたか?」
「はい、もちろんで御座いますご主人様。ほらマノン!さっさとお前の汚いパンツをお見せしなさい!」
未穂にそう怒鳴りつけられ、正治は改めて今の自分の立場を思い知った。
「は、はい・・・・・」
もう逆らう事も出来ず、正治は超ミニにされた制服のプリーツスカートに手を掛ける。
「ほら、どうした!さっさと見せろ!」
先程散々恥ずかしい姿を晒したが、それでもその行為は激しい羞恥を伴った。
「は、はい・・・・」
ゆっくりと屈辱に耐えながら正治はスカートを捲る。中から現れたのは先程未穂に渡されたいかにも女学生用といった真っ白のコットンショーツだ。臍の下にはピンク色のリボン。その横にはレースがあしらわれ、その横には
「あはははははははっ!!」
恭平と結衣が大きな口を開けて爆笑する。
正治の穿かされたショーツにはまるで幼稚園の子供の様に大きく『森川マノン』と書かれていたからだ。
「わははははっ!これなら迷子になってもすぐに飼い主に連絡が取れるな。じゃあ、行くとするか。」
恭平は手に持ったキーケースをじゃらりと鳴らす。
「行く?」
正治の怯えた声が彼には堪らない。
「そうだ。これから四人で食事に行こうじゃないか。いや、三人と一匹でだな。くくくくくっ・・・・おらっ、さっさと出ろっ!」
良く見知った自室の前の廊下にセーラー服姿のまま玄関から突き出され、正治はもうそれが現実だとは認識したく無かった。
「あ、あら?森川・・・・さん?」
そこに偶然通りかかった一人の可愛らしい女子高生。
彼女は正治と全く同じ制服を着ていた。
まっことゆっくりですが続けて参りますので宜しくお願いします。
「ほらっ、さっさとこれに着替えるのよ。」
未穂から受け取った衣服を目にし、正治は今日何度目かの驚愕を味わう。
「ちょ、ちょっと待て!俺にこれを着ろっていうのか?」
妻である筈の未穂に詰め寄る正治。だが、彼女はもう正治のものでは無かった。
「先輩に無礼よ!」
躊躇無く未穂から平手打ちを頬に受け、正治は呆然となった。
「大体、いまでもこんな格好して今更何が恥ずかしいのよ。男の癖にメイド服着て、恭平様の精液と自分のお漏らしででべたべたに汚しちゃってる癖に。」
そう言われては返す言葉も無かった。
「くっ・・・・」
だがまだ少しプライドを残した正治は拳を握ってその衣装を見つめる。それは男性が着るには余りにも恥ずかしい衣装、女子学生用のセーラー服だったからだ。
「あははは、意外と似合うじゃないか。」
二人が着替え終わった姿を目にした恭平が高らかに笑う。
「ホント、制服の魔力って怖いわね。あんたも年増の癖にちゃんと女子高生に見えるわよ。」
結衣までもが未穂を揶揄するが、未穂は殊勝にも年下の小娘に向かって頭を下げていた。
「未穂、きちんと下着も穿かせたか?」
「はい、もちろんで御座いますご主人様。ほらマノン!さっさとお前の汚いパンツをお見せしなさい!」
未穂にそう怒鳴りつけられ、正治は改めて今の自分の立場を思い知った。
「は、はい・・・・・」
もう逆らう事も出来ず、正治は超ミニにされた制服のプリーツスカートに手を掛ける。
「ほら、どうした!さっさと見せろ!」
先程散々恥ずかしい姿を晒したが、それでもその行為は激しい羞恥を伴った。
「は、はい・・・・」
ゆっくりと屈辱に耐えながら正治はスカートを捲る。中から現れたのは先程未穂に渡されたいかにも女学生用といった真っ白のコットンショーツだ。臍の下にはピンク色のリボン。その横にはレースがあしらわれ、その横には
「あはははははははっ!!」
恭平と結衣が大きな口を開けて爆笑する。
正治の穿かされたショーツにはまるで幼稚園の子供の様に大きく『森川マノン』と書かれていたからだ。
「わははははっ!これなら迷子になってもすぐに飼い主に連絡が取れるな。じゃあ、行くとするか。」
恭平は手に持ったキーケースをじゃらりと鳴らす。
「行く?」
正治の怯えた声が彼には堪らない。
「そうだ。これから四人で食事に行こうじゃないか。いや、三人と一匹でだな。くくくくくっ・・・・おらっ、さっさと出ろっ!」
良く見知った自室の前の廊下にセーラー服姿のまま玄関から突き出され、正治はもうそれが現実だとは認識したく無かった。
「あ、あら?森川・・・・さん?」
そこに偶然通りかかった一人の可愛らしい女子高生。
彼女は正治と全く同じ制服を着ていた。
近況報告
放置ですいません。
ようやく久しぶりに更新してみました。
SM色強すぎかもしれませんが、マイペースで更新しますので宜しくお願いします。
あと宣伝ですが、5月5日に新作がDL販売開始されます。
こちらはちょっとソフトな憑依ものですが、巨乳少女にされた男の子がちょっと乱暴に後輩から犯されたりしますのでよろしければお読み頂ければありがたいです。
それではまた宜しくお願い致します。
ようやく久しぶりに更新してみました。
SM色強すぎかもしれませんが、マイペースで更新しますので宜しくお願いします。
あと宣伝ですが、5月5日に新作がDL販売開始されます。
こちらはちょっとソフトな憑依ものですが、巨乳少女にされた男の子がちょっと乱暴に後輩から犯されたりしますのでよろしければお読み頂ければありがたいです。
それではまた宜しくお願い致します。
奪われた妻と俺の性08
「えっ!?」
その言葉の持つ意味のあまりの恐ろしさを、正治は現実として受け止めることが出来なかった。彼はきょとんとした目で恭平を見上げる。
「聞こえ無かったのか?それを飲めと言っているんだ。」
威圧する様な低い声で言われ、正治はようやくその意味を悟る。
「そ、そんな・・・・」
「どうした?」
戸惑う正治を見て恭平はサディストの血を熱くさせた様だった。
「遠慮せずに飲んでいいんだぞ。奴隷メイドのお前にとっては贅沢すぎるその飲み物をな・・・・ほら、どうした?」
そう言われてもそんな事が出来る筈が無い。なにしろ手に持っているのは憎い男の精液と小便が満たされたコップなのだ。たとえ正治がSMビデオの撮影に来たAV女優だったとしても拒否するだろう。
「い、イヤだ・・・・・」
震える声で正治はそれを拒否する。いくらなんでも悪い冗談過ぎる。
「ん?」
だが恭平は本気らしく、その形の良い眉を顰めて未穂に言い付けた。
「おい未穂、皿を用意してやれ。マノンがこのままでは恐れ多くて飲めないらしい。」
「はい、ご主人様!」
呆気にとられる正治をよそに未穂は立ち上がって台所からなにやら取り出す。
「あっ!」
それはどうみてもペット用の赤い皿だった。
「さあ、これなら飲めるわよね。せっかくの恭平様の体液だもんねぇ。」
未穂は正治からコップを奪うと、ペット皿にその濁った液体をなみなみと注いでいく。
「うっ!」
まだ生暖かい液体の発する生臭い匂いが正治の鼻腔をくすぐる。いや、くすぐるというよりそれは強烈な刺激臭だった。
「馬鹿な子ね、鼻を摘んで一気に飲めばいいものを、躊躇しているからこんな羽目になるのよ。」
未穂がそう言ってクスクスと笑った。
「ほら、これ以上我が儘いうと、先輩メイドの私が許さないわよ!さっさと舐め取りなさい!どうせこれからマノンの食事は全てそれになるんだからね!」
未穂はそう言って、夫の後頭部を押さえてその更に押しつけた。
「うぶぅっ!」
突然の事に抵抗も出来ず、正治はその液体に鼻先を突っ込んでしまう。
「う・・・うっ・・うぇぇえっ!!」
まるで大きな痰壷で顔を洗っているかの様な感覚に、正治は五感の全てに鳥肌を立たせた。
「ほら、さっさと舐めなさい!」
慌てて顔を上げた正治の尻を、いつのまにか後ろに立っていた結衣が先程の布団叩きでぶつ。
「ひぃっ!!」
「いい加減見てるだけにも飽きたわ。ほら、さっさと全部舐め取らないと尻の肉が無くなっちゃうよっ!」
「あひぃっ!!」
正治のスカートを捲り上げショーツをずらすと、先程とは比べものにならない力で結衣はその布団叩きを彼の尻に打ち据えた。
「な、舐めます!舐めますからぁっ!!」
あまりの痛みに遂に正治は屈服した。
「うっ・・・うっ・・・うぅっ・・・」
恭平と二人の年下女性に苦笑されながら正治はその液体に舌を這わす。
「うぇぇぇっ・・・」
それは苦いなどという生やさしい味では無かった。まるで世界中の発酵食品をぐちゃぐちゃに混ぜて腐らせたものを口に流し込んでいる様だ。おまけに精液まで加えられている為、そのぬめぬめした液体が舌にまとわりついて飲み干すことさえままならない。両手は床につくことを命じられた為、鼻を塞ぐこともできずに鼻先にまでその粘液が絡みつく。
「ぴしゃっ・・・ぴしゃっ・・・・」
それでも正治はそれを犬の様に舐めとり続けなければならなかった。だが少しばかりその味に耐性がついた瞬間に恭平が彼を辱める。
「どうだ、マノン俺の小便と精液のミックスジュースは旨いか?」
「あっ・・はっ・・・はいっ・・・うべぇっ・・・・」
自分の舐めているものが確かに目の前の男の排泄物だということを思い出さされ、正治の体に再び嫌悪感が走った。
「んふふ・・・・初めは辛いかもしれないけどそのうち慣れるわよ。私みたいにね。」
未穂が静かな声で恐ろしい事を言った。妻はいったいどこまで『調教』されているのだろうか・・・・。正治は自分の立場も忘れてうっすらとそんな事を考えていた。
だが、彼にはもはや妻を心配する余裕すらも与えられなかった。
「結衣、こいつのエサが終わったら俺達も食事に出掛けるか。」
「そうね、私もお腹すいたわ。」
その会話を聞きながら正治はようやく、しばらくの間でも解放されるのかと安堵した。しかし・・・・
「未穂、外出の用意をしろ、いつもの服装でな・・・・もちろん、新入りメイドの分もだ。」
まだ少し皿に残る恭平の小便を味わいながら、正治は震えが止まらなかった。
その言葉の持つ意味のあまりの恐ろしさを、正治は現実として受け止めることが出来なかった。彼はきょとんとした目で恭平を見上げる。
「聞こえ無かったのか?それを飲めと言っているんだ。」
威圧する様な低い声で言われ、正治はようやくその意味を悟る。
「そ、そんな・・・・」
「どうした?」
戸惑う正治を見て恭平はサディストの血を熱くさせた様だった。
「遠慮せずに飲んでいいんだぞ。奴隷メイドのお前にとっては贅沢すぎるその飲み物をな・・・・ほら、どうした?」
そう言われてもそんな事が出来る筈が無い。なにしろ手に持っているのは憎い男の精液と小便が満たされたコップなのだ。たとえ正治がSMビデオの撮影に来たAV女優だったとしても拒否するだろう。
「い、イヤだ・・・・・」
震える声で正治はそれを拒否する。いくらなんでも悪い冗談過ぎる。
「ん?」
だが恭平は本気らしく、その形の良い眉を顰めて未穂に言い付けた。
「おい未穂、皿を用意してやれ。マノンがこのままでは恐れ多くて飲めないらしい。」
「はい、ご主人様!」
呆気にとられる正治をよそに未穂は立ち上がって台所からなにやら取り出す。
「あっ!」
それはどうみてもペット用の赤い皿だった。
「さあ、これなら飲めるわよね。せっかくの恭平様の体液だもんねぇ。」
未穂は正治からコップを奪うと、ペット皿にその濁った液体をなみなみと注いでいく。
「うっ!」
まだ生暖かい液体の発する生臭い匂いが正治の鼻腔をくすぐる。いや、くすぐるというよりそれは強烈な刺激臭だった。
「馬鹿な子ね、鼻を摘んで一気に飲めばいいものを、躊躇しているからこんな羽目になるのよ。」
未穂がそう言ってクスクスと笑った。
「ほら、これ以上我が儘いうと、先輩メイドの私が許さないわよ!さっさと舐め取りなさい!どうせこれからマノンの食事は全てそれになるんだからね!」
未穂はそう言って、夫の後頭部を押さえてその更に押しつけた。
「うぶぅっ!」
突然の事に抵抗も出来ず、正治はその液体に鼻先を突っ込んでしまう。
「う・・・うっ・・うぇぇえっ!!」
まるで大きな痰壷で顔を洗っているかの様な感覚に、正治は五感の全てに鳥肌を立たせた。
「ほら、さっさと舐めなさい!」
慌てて顔を上げた正治の尻を、いつのまにか後ろに立っていた結衣が先程の布団叩きでぶつ。
「ひぃっ!!」
「いい加減見てるだけにも飽きたわ。ほら、さっさと全部舐め取らないと尻の肉が無くなっちゃうよっ!」
「あひぃっ!!」
正治のスカートを捲り上げショーツをずらすと、先程とは比べものにならない力で結衣はその布団叩きを彼の尻に打ち据えた。
「な、舐めます!舐めますからぁっ!!」
あまりの痛みに遂に正治は屈服した。
「うっ・・・うっ・・・うぅっ・・・」
恭平と二人の年下女性に苦笑されながら正治はその液体に舌を這わす。
「うぇぇぇっ・・・」
それは苦いなどという生やさしい味では無かった。まるで世界中の発酵食品をぐちゃぐちゃに混ぜて腐らせたものを口に流し込んでいる様だ。おまけに精液まで加えられている為、そのぬめぬめした液体が舌にまとわりついて飲み干すことさえままならない。両手は床につくことを命じられた為、鼻を塞ぐこともできずに鼻先にまでその粘液が絡みつく。
「ぴしゃっ・・・ぴしゃっ・・・・」
それでも正治はそれを犬の様に舐めとり続けなければならなかった。だが少しばかりその味に耐性がついた瞬間に恭平が彼を辱める。
「どうだ、マノン俺の小便と精液のミックスジュースは旨いか?」
「あっ・・はっ・・・はいっ・・・うべぇっ・・・・」
自分の舐めているものが確かに目の前の男の排泄物だということを思い出さされ、正治の体に再び嫌悪感が走った。
「んふふ・・・・初めは辛いかもしれないけどそのうち慣れるわよ。私みたいにね。」
未穂が静かな声で恐ろしい事を言った。妻はいったいどこまで『調教』されているのだろうか・・・・。正治は自分の立場も忘れてうっすらとそんな事を考えていた。
だが、彼にはもはや妻を心配する余裕すらも与えられなかった。
「結衣、こいつのエサが終わったら俺達も食事に出掛けるか。」
「そうね、私もお腹すいたわ。」
その会話を聞きながら正治はようやく、しばらくの間でも解放されるのかと安堵した。しかし・・・・
「未穂、外出の用意をしろ、いつもの服装でな・・・・もちろん、新入りメイドの分もだ。」
まだ少し皿に残る恭平の小便を味わいながら、正治は震えが止まらなかった。
奪われた妻と俺の性07
「あらあら、お漏らし?躾ができてない子ね・・・」
未穂はそう言いながら指先で正治のペニスを弄ぶ。
「おいおい、それくらいにしておいてやれ。俺のチンポを噛み切られでもしたらたまらんからな・・・・おい、小便漏らしてるヒマがあったら、もっと丁寧にしゃぶれっ!」
「はっ!はぁいっ!!」
妻と後輩の前でメイド服姿のままお漏らしをしてしまうという、考えられない様な屈辱を味わった正治の頭はもうどうにかなりそうだった。しかしそんな状態でも彼は必死に恭平に奉仕し続けるしかなかった。
「ん・・んんっ・・・」
正治は必死に頭を前後に振った。もう恭平のペニスは今にも達しそうである。『じゅぶっじゅぶっ』という卑猥な音が部屋に鳴り響き、更に正治の羞恥心を責め続けた。
「ん・・・よしっ・・・・出すぞっ・・・溢したらお仕置きだぞっ・・・」
その言葉から数秒後、恭平の彼の猛り狂ったペニスの先から白い液がほとばしる。
「んんっ!!んんっ!!!んんんんっ!!」
自分の経験からは考えられない程の勢いで飛び出した精液を喉の奥に発射され、正治は息も絶え絶えになりながら恭平の股間から逃げようとする。
「んんんぅぅんんぅぅうっ----っ!!」
しかし絶頂のまっただ中の恭平は正治の頭をしっかりとつかみあげ、生暖かく生臭い液を正治の口内にまき散らした。
「う・・・ううぇぇぇーーーっ・・・・」
今まで味わった事のないほどの臭い液を口の中一杯に排出され、ようやく口からペニスを引き抜かれても正治の嘔吐感は収まらなかった。
「どう?恭平様のせーえきはおいしいでしょ?あんたのと違ってもの凄く濃くって一杯でるしねぇ・・・あんたの包茎チンコじゃ、『ドピュッ』ていうより『ちろちろ』ってこぼれ落ちるくらいだったもんねぇ・・・」
未穂は正治を罵りながら、必死に吐き気に耐える正治を見て笑う。
「う、うえぇっ!!」
しかし精飲などというものは簡単にできるものではない、それをするのが男性、しかも妻を寝取った憎き相手の精液ならなおさらだ。
「えぇっぇぇ・・・っ!!」
そのあまりの匂いと量に正治は思わず、口に溜まった精液を床に溢してしまう。
「だめっ!全部飲みなさい!」
未穂が正治の口を押さえるが、流れ落ちる精液は正治の漏らした小便の上に糸を引いてしたたり墜ちてしまった。
「馬鹿な奴だ・・・。」
恭平は座ったまま呟いた。
「あっ、申し訳ありません。」
未穂がそう言うと、恭平の股間のまだ勃起したままのペニスを掃除し始める。
「おいおい、自分のフェラしたチンコを嫁に掃除させるとは出来の悪い亭主だなぁ・・・みろよ、お前の嫁がこんなにうまそうに俺のチンコをおしゃぶりしてるぜ。あっはっはっはっはっ!」
正治はまだ口の中に残るネバネバした液の気持ち悪さを必死に我慢しながら顔を上げる。確かにそこには幸福そうな表情で恭平のペニスを貪る妻の姿があった。
「おい結衣、そこのコップをこいつに渡してやれ・・・そうだその大きな奴だ。」
「何に使うのよ?」
そう言いながらも結衣はニヤニヤしながら、洗い場の傍に置いてあった大きなコップを取ると正治に渡した。
「マノン、お前の溢した精液を全部そのコップに入れるんだ。」
「えっ?」
まだ放心状態の正治は意味が分からず恭平に聞き返す。
「聞こえ無かったのか?ご主人様の大切な精液を無駄にする事は許さん。全部手でくみ取って、コップに入れろと言ってるんだ!」
「は、はいっ!!」
恭平の怒鳴り声に正治は慌てて指示された通り両手でその白い液体を掬う。男の精液など手で触るなど不愉快だったが、飲まされるよりはマシだ。正治は掬っても掬ってもこぼれ落ちる液体を必死にコップに移し替えた。
「出来ました・・・。」
十分後、コップは恭平の出した精液、そして正治の漏らした小便で満たされた。
「まだお前の漏らした小便が残っているが仕方無いな・・・。」
恭平は床を見てニヤリと笑うと、自分の股間を指さした。
「おい、コップをここに持ってこい。」
訳が分からないまま正治は恭平のペニスの下にコップを差し出す。
「よし、そこだ・・・そのままじっとしていろ。」
正治がまさかと思ったその瞬間、恭平のペニスの先から小便がほとばしる。
「ひゃっ!!」
まだ半分勃起したままのペニスから放出された小便が顔にかかり、正治は思わず顔を背けた。
「こらっ!避けるとは何事だ!きちんとコップで受け止めろっ!」
恭平の声に正治は必死にコップで正治の小便を受け続けた。
「よし、いいだろう。」
数秒後、大きなコップは恭平の精液と小便で満たされた。それが何に使われるのかその時の正治には想像もつかなかった。彼はただ自分の右手に持たれた限りなく汚らしい液体を一刻も早くトイレにでも捨て去りたい気分だったのだ。しかしそんな正治に向かって恭平は恐ろしい言葉を吐く。
「おいマノン、それを飲み干すんだ・・・全部な。」
未穂はそう言いながら指先で正治のペニスを弄ぶ。
「おいおい、それくらいにしておいてやれ。俺のチンポを噛み切られでもしたらたまらんからな・・・・おい、小便漏らしてるヒマがあったら、もっと丁寧にしゃぶれっ!」
「はっ!はぁいっ!!」
妻と後輩の前でメイド服姿のままお漏らしをしてしまうという、考えられない様な屈辱を味わった正治の頭はもうどうにかなりそうだった。しかしそんな状態でも彼は必死に恭平に奉仕し続けるしかなかった。
「ん・・んんっ・・・」
正治は必死に頭を前後に振った。もう恭平のペニスは今にも達しそうである。『じゅぶっじゅぶっ』という卑猥な音が部屋に鳴り響き、更に正治の羞恥心を責め続けた。
「ん・・・よしっ・・・・出すぞっ・・・溢したらお仕置きだぞっ・・・」
その言葉から数秒後、恭平の彼の猛り狂ったペニスの先から白い液がほとばしる。
「んんっ!!んんっ!!!んんんんっ!!」
自分の経験からは考えられない程の勢いで飛び出した精液を喉の奥に発射され、正治は息も絶え絶えになりながら恭平の股間から逃げようとする。
「んんんぅぅんんぅぅうっ----っ!!」
しかし絶頂のまっただ中の恭平は正治の頭をしっかりとつかみあげ、生暖かく生臭い液を正治の口内にまき散らした。
「う・・・ううぇぇぇーーーっ・・・・」
今まで味わった事のないほどの臭い液を口の中一杯に排出され、ようやく口からペニスを引き抜かれても正治の嘔吐感は収まらなかった。
「どう?恭平様のせーえきはおいしいでしょ?あんたのと違ってもの凄く濃くって一杯でるしねぇ・・・あんたの包茎チンコじゃ、『ドピュッ』ていうより『ちろちろ』ってこぼれ落ちるくらいだったもんねぇ・・・」
未穂は正治を罵りながら、必死に吐き気に耐える正治を見て笑う。
「う、うえぇっ!!」
しかし精飲などというものは簡単にできるものではない、それをするのが男性、しかも妻を寝取った憎き相手の精液ならなおさらだ。
「えぇっぇぇ・・・っ!!」
そのあまりの匂いと量に正治は思わず、口に溜まった精液を床に溢してしまう。
「だめっ!全部飲みなさい!」
未穂が正治の口を押さえるが、流れ落ちる精液は正治の漏らした小便の上に糸を引いてしたたり墜ちてしまった。
「馬鹿な奴だ・・・。」
恭平は座ったまま呟いた。
「あっ、申し訳ありません。」
未穂がそう言うと、恭平の股間のまだ勃起したままのペニスを掃除し始める。
「おいおい、自分のフェラしたチンコを嫁に掃除させるとは出来の悪い亭主だなぁ・・・みろよ、お前の嫁がこんなにうまそうに俺のチンコをおしゃぶりしてるぜ。あっはっはっはっはっ!」
正治はまだ口の中に残るネバネバした液の気持ち悪さを必死に我慢しながら顔を上げる。確かにそこには幸福そうな表情で恭平のペニスを貪る妻の姿があった。
「おい結衣、そこのコップをこいつに渡してやれ・・・そうだその大きな奴だ。」
「何に使うのよ?」
そう言いながらも結衣はニヤニヤしながら、洗い場の傍に置いてあった大きなコップを取ると正治に渡した。
「マノン、お前の溢した精液を全部そのコップに入れるんだ。」
「えっ?」
まだ放心状態の正治は意味が分からず恭平に聞き返す。
「聞こえ無かったのか?ご主人様の大切な精液を無駄にする事は許さん。全部手でくみ取って、コップに入れろと言ってるんだ!」
「は、はいっ!!」
恭平の怒鳴り声に正治は慌てて指示された通り両手でその白い液体を掬う。男の精液など手で触るなど不愉快だったが、飲まされるよりはマシだ。正治は掬っても掬ってもこぼれ落ちる液体を必死にコップに移し替えた。
「出来ました・・・。」
十分後、コップは恭平の出した精液、そして正治の漏らした小便で満たされた。
「まだお前の漏らした小便が残っているが仕方無いな・・・。」
恭平は床を見てニヤリと笑うと、自分の股間を指さした。
「おい、コップをここに持ってこい。」
訳が分からないまま正治は恭平のペニスの下にコップを差し出す。
「よし、そこだ・・・そのままじっとしていろ。」
正治がまさかと思ったその瞬間、恭平のペニスの先から小便がほとばしる。
「ひゃっ!!」
まだ半分勃起したままのペニスから放出された小便が顔にかかり、正治は思わず顔を背けた。
「こらっ!避けるとは何事だ!きちんとコップで受け止めろっ!」
恭平の声に正治は必死にコップで正治の小便を受け続けた。
「よし、いいだろう。」
数秒後、大きなコップは恭平の精液と小便で満たされた。それが何に使われるのかその時の正治には想像もつかなかった。彼はただ自分の右手に持たれた限りなく汚らしい液体を一刻も早くトイレにでも捨て去りたい気分だったのだ。しかしそんな正治に向かって恭平は恐ろしい言葉を吐く。
「おいマノン、それを飲み干すんだ・・・全部な。」
奪われた妻と俺の性06
「んぐっ・・・・んぐっ・・・」
正治は必死に、それこそ死んだ思いで後輩のペニスを舐め続けた。
「なにしてるんだ、この下手くそがぁっ!」
しかし恭平の口から出るのはそんな思いさえ壊してしまう酷い言葉だった。
「おい、お前の口は今は性器なんだぜ?分かってるのかよ?」
正治は口から唾液を滴らせながら黙って頷く。
「なら、もうちょっと一生懸命奉仕しやがれ!男なんだから男の感じるところは分かるだろうがっ!」
「ひゃ・・・ひゃいっ・・・」
正治は力なくそう返事すると、再度恭平のペニスを口に含んだ。
『もう射精させるまでは許してもらえないかもしれない・・・・。』
ようやくそう覚悟した正治は、今まで躊躇していた舌先を恭平のペニスのカリ部分に這わす。
「うっ・・ううぇっ・・・」
そこに溜まった恥垢の強烈な味に吐き気を催しながらも、正治はその行為を続けざるを得ない。
「うんっ・・よしっ・・・やれば出来るじゃないか、マノン・・・。」
恭平のその言葉通り彼のペニスは徐々に大きさを増していく。自分の舌技で恭平がペニスを勃起させていると想像すると、正治は死んでしまいたい程の屈辱感に襲われた。
「ほらっ・・・もっと、唇も使って奉仕しろ・・・。」
恭平のペニスはあっという間に小さな正治の口内を埋め尽くす。言われた通り唇で恭平のペニスを咥え前後に頭を動かしながら、正治は自分がまるで女性器そのものになってしまったかの様に錯覚した。
「ん・・・んぐぐぐぅっ・・・」
しかしそんな妄想をしている間もなく、恭平の若く凶暴なペニスはあっという間に正治の口内から食道に侵入する。
「んあぁっ!・・・・はぁっ・・はぁっ・・・」
満足に息も出来ない状況に陥った正治は思わず口を離そうとするが、がっちりと恭平に頭を掴まれ息絶え絶えになりながらペニスをしゃぶり続けるしかなかった。
「ホント、おいしそうにおしゃぶりするわねぇ。」
未穂が羨ましそうに夫であるはずの正治を見て笑った。
「ねぇ、正治・・・マノンったら、本当はこうやって女の子の格好して、ペニスをおしゃぶりしてみたかったんじゃないのぉ?」
未穂はそう言って正治のスカートに腕を入れる。
「んんっ!!んっ!!!」
抵抗する正治だったが、恭平に頭部を固定されていてはどうする事も出来ない。未穂の指は正治の穿いているショーツの上から彼のペニスをくすぐる。
「んふふ・・・こんな小さなペニスで私を抱きながら・・・実は男の人に抱かれる事を想像して興奮してたんじゃない・・・・この変態!!」
「ひひゃぁひゃぁぅぅっ!!」
未穂が力の加減無く正治の睾丸を握りしめ、彼は恭平のペニスを咥えながら声にならない悲鳴を上げた。
「馬鹿野郎っ!!歯を立てるなっ!」
恭平は慌てて正治の口からペニスを引き抜くと、彼の左頬を平手打ちする。
「も、申し訳ありませんっ・・・・・ひぎゃああぁぁぁっ!!」
未穂が更に睾丸を潰すが如く握り、頬と股間、双方の痛みに正治は絶叫する。しかしそんな悲鳴など無視して恭平はもう一度正治の口内に己の猛り狂ったものを突き刺した。
「おらっ!今度歯立てたら全部引っこ抜いてフェラ専用の口にしてやるからなっ!」
「ひゃ!ひゃいっ!!」
あまりの恐怖に正治は震えながら三度恭平のものに舌を這わす。
「ねぇ、恭平様のおいしい?」
未穂はそんな夫を横目で見ながら呟く様に言った。
「そんなに男のチンポがおいしいならこんなものはいらないわよねぇ?」
「えっ!?」
正治が驚くヒマもなく、未穂は今度は彼のペニスをショーツの上から力の限り踏みつけた。
「ひぐぎゃあああぁぁぁっ!!ひっ!・・・ひぐっ・・・・」
正治の穿いている薄いピンク色のメイド服のスカートが次第に濃いピンク色に染まり、フローリングの床に生暖かい液体が広がる。
声も出ないほどの恐怖の中正治は失禁してしまっていた。
正治は必死に、それこそ死んだ思いで後輩のペニスを舐め続けた。
「なにしてるんだ、この下手くそがぁっ!」
しかし恭平の口から出るのはそんな思いさえ壊してしまう酷い言葉だった。
「おい、お前の口は今は性器なんだぜ?分かってるのかよ?」
正治は口から唾液を滴らせながら黙って頷く。
「なら、もうちょっと一生懸命奉仕しやがれ!男なんだから男の感じるところは分かるだろうがっ!」
「ひゃ・・・ひゃいっ・・・」
正治は力なくそう返事すると、再度恭平のペニスを口に含んだ。
『もう射精させるまでは許してもらえないかもしれない・・・・。』
ようやくそう覚悟した正治は、今まで躊躇していた舌先を恭平のペニスのカリ部分に這わす。
「うっ・・ううぇっ・・・」
そこに溜まった恥垢の強烈な味に吐き気を催しながらも、正治はその行為を続けざるを得ない。
「うんっ・・よしっ・・・やれば出来るじゃないか、マノン・・・。」
恭平のその言葉通り彼のペニスは徐々に大きさを増していく。自分の舌技で恭平がペニスを勃起させていると想像すると、正治は死んでしまいたい程の屈辱感に襲われた。
「ほらっ・・・もっと、唇も使って奉仕しろ・・・。」
恭平のペニスはあっという間に小さな正治の口内を埋め尽くす。言われた通り唇で恭平のペニスを咥え前後に頭を動かしながら、正治は自分がまるで女性器そのものになってしまったかの様に錯覚した。
「ん・・・んぐぐぐぅっ・・・」
しかしそんな妄想をしている間もなく、恭平の若く凶暴なペニスはあっという間に正治の口内から食道に侵入する。
「んあぁっ!・・・・はぁっ・・はぁっ・・・」
満足に息も出来ない状況に陥った正治は思わず口を離そうとするが、がっちりと恭平に頭を掴まれ息絶え絶えになりながらペニスをしゃぶり続けるしかなかった。
「ホント、おいしそうにおしゃぶりするわねぇ。」
未穂が羨ましそうに夫であるはずの正治を見て笑った。
「ねぇ、正治・・・マノンったら、本当はこうやって女の子の格好して、ペニスをおしゃぶりしてみたかったんじゃないのぉ?」
未穂はそう言って正治のスカートに腕を入れる。
「んんっ!!んっ!!!」
抵抗する正治だったが、恭平に頭部を固定されていてはどうする事も出来ない。未穂の指は正治の穿いているショーツの上から彼のペニスをくすぐる。
「んふふ・・・こんな小さなペニスで私を抱きながら・・・実は男の人に抱かれる事を想像して興奮してたんじゃない・・・・この変態!!」
「ひひゃぁひゃぁぅぅっ!!」
未穂が力の加減無く正治の睾丸を握りしめ、彼は恭平のペニスを咥えながら声にならない悲鳴を上げた。
「馬鹿野郎っ!!歯を立てるなっ!」
恭平は慌てて正治の口からペニスを引き抜くと、彼の左頬を平手打ちする。
「も、申し訳ありませんっ・・・・・ひぎゃああぁぁぁっ!!」
未穂が更に睾丸を潰すが如く握り、頬と股間、双方の痛みに正治は絶叫する。しかしそんな悲鳴など無視して恭平はもう一度正治の口内に己の猛り狂ったものを突き刺した。
「おらっ!今度歯立てたら全部引っこ抜いてフェラ専用の口にしてやるからなっ!」
「ひゃ!ひゃいっ!!」
あまりの恐怖に正治は震えながら三度恭平のものに舌を這わす。
「ねぇ、恭平様のおいしい?」
未穂はそんな夫を横目で見ながら呟く様に言った。
「そんなに男のチンポがおいしいならこんなものはいらないわよねぇ?」
「えっ!?」
正治が驚くヒマもなく、未穂は今度は彼のペニスをショーツの上から力の限り踏みつけた。
「ひぐぎゃあああぁぁぁっ!!ひっ!・・・ひぐっ・・・・」
正治の穿いている薄いピンク色のメイド服のスカートが次第に濃いピンク色に染まり、フローリングの床に生暖かい液体が広がる。
声も出ないほどの恐怖の中正治は失禁してしまっていた。
奪われた妻と俺の性05
「そうか、いいだろう。」
恭平はそう言うと、汚らしい足を未穂の前に投げ出す。
「頂かせて頂きます。」
未穂はその足を丁寧に両手で持ち上げると、躊躇無く舐め始める。まずは足の親指から垢の溜まった指の間まで。その姿を見ているだけで正治は胸が張り裂けそうだった。
「どうだ、旨いか?」
「はい、大変美味で御座います、ご主人様。」
未穂は笑って恭平に言う。そんなものが旨いはずが無い。臭くて苦くて不衛生なものを舐めさせられながら笑っている妻を見て、正治は恭平の意地悪さに心底腹を立てるが、彼には妻に対して同情している余裕など無かったのだ。
「おい、お前はどうする?」
「はっ?」
恭平の問いに正治は彼の目の前にひれ伏したまま聞き返した。
「折角のご主人様に奉仕するチャンスを別のメイドに取られたんだ。お前も何か奉仕しないと気がきではないだろう?」
「い、いえ・・・そんな事は・・・。」
それは正治の本心だったが、恭平がそんな事で許す筈も無かった。
「まぁ無理するな。お前は今日から入った新入りメイドだからな。ご主人様にご奉仕したくて仕方が無い。そうだろう?」
「い・・・いえ・・・・。」
「何だ!?ハッキリ言え!」
正治の小さな抗いの言葉は恭平の怒鳴り声によってかき消された。
「い・・いえ・・・奉仕・・・したいです・・・。」
恭平の怒気に押された正治は思わず、そう返事をしてしまった。
「そうかそうか、そんなに俺に奉仕したいんだな。」
恭平は笑って結衣を見た。
「おい、結衣。実に感心な新米メイドだな。折角だから夜まで待っておこうと思っていた奉仕をさせてやるか。」
結衣はクスクスと笑って言う。
「いい考えね。新米メイドの忠誠心を確かめるのには丁度良い機会だわ。」
何をさせられるのか分からず、怯える正治を恭平は傍にくる様に命じる。正治は膝をついたまま恭平の足下に近づいた。妻が憎き男の足の指を丁寧にしゃぶる音が正治の神経を逆なでる。
「じゃあ夫婦揃ってご奉仕してもらおうか。マノン、お前が奉仕するのはこれだ。」
恭平は面白くてたまらないといった表情でズボンのボタンを外すと、そのままチャックとトランクスをずり下げ、己の凶悪なペニスをあらわにした。
「あっ・・・あぁっ・・・・あぁっ!!・・・・」
自分が何に対して奉仕するかと言うことを悟り、正治の顔が真っ青になる。
「どうした?ご主人様のペニスに対して奉仕するのは、メイドとして一番の悦びだろうが?」
「ひっ!ひいっ!」
思わず後ずさりして逃げようとした正治の背中を結衣が押さえる。腰が抜けた彼は結衣の手で再び恭平の前に押しやられた。勃起こそしていないが、自分とは全く異なるズル剥けの赤黒いペニスを目の当たりにし、正治は震えが止まらなかった。
「ほら、遠慮する事はない。存分にしゃぶっていいんだぞ。」
恭平が指でペニスの根本をつかんで正治の頬を張る。男臭い匂いが鼻につき、正治はもう死にたい程の感覚に襲われた。
「どうした?それともこっちも未穂に舐めさせたいのか?」
その言葉は正治に少しだけ理性を取り戻させた。愛する妻がこの男のペニスを舐めるなんて考えたくもない光景だった。
「・・・・・分かった・・・。」
正治はそう小さく呟くと、目の前の男のものを恐る恐る手にとってみる。
「そうかそうか、その気になったか。じゃあしゃぶらせてやろう。もちろん俺が射精するまで許さないからな。ほら、さっさと咥えろ、この淫乱メイドがっ!」
「は、はいっ・・・」
正治は涙ながらに、その恭平のペニスに口を付けた。
「う、うえっ・・・」
生臭い匂いが口内に広がり、彼は嘔吐しそうになる。
「ははぁ、さてはフェラは初体験か。」
恭平が白々しく驚いた様な顔をする。
「しかしフェラ奉仕はメイドにとって基本的な事だ。これぐらい出来ないと話にならないぞ・・・おら!もっと口に含むんだよ!」
「ひゃいっ・・・」
正治は息を止めてその肉棒を喉の奥まで咥え込んだ。
「ご主人様、私もー。」
気が付けば隣では未穂が羨ましそうに自分を見ている。そういえば、何度か頼んだ事はあるが、未穂が自分に対しては決して『奉仕』してくれなかった事を正治は思い出した。
「お前は後からだ。今は亭主が男のチンコを舐めるところを見て楽しんでいるんだな。」
恭平の言葉に、未穂が拗ねた様に言う。
「ちょっと、正治ったら男のクセメイド服着て男のチンポ咥えちゃって・・・プライドってもんが無いの?言っておくけど、そのおちんちんは私のものなんだからね。」
以前では考えられない妻の口から飛び出す卑猥な言葉に正治は愕然とするが、目の前の現実からは逃げる事は出来なかった。『妻を正気に戻す為』彼は、同性のペニスを舐め続けた。
恭平はそう言うと、汚らしい足を未穂の前に投げ出す。
「頂かせて頂きます。」
未穂はその足を丁寧に両手で持ち上げると、躊躇無く舐め始める。まずは足の親指から垢の溜まった指の間まで。その姿を見ているだけで正治は胸が張り裂けそうだった。
「どうだ、旨いか?」
「はい、大変美味で御座います、ご主人様。」
未穂は笑って恭平に言う。そんなものが旨いはずが無い。臭くて苦くて不衛生なものを舐めさせられながら笑っている妻を見て、正治は恭平の意地悪さに心底腹を立てるが、彼には妻に対して同情している余裕など無かったのだ。
「おい、お前はどうする?」
「はっ?」
恭平の問いに正治は彼の目の前にひれ伏したまま聞き返した。
「折角のご主人様に奉仕するチャンスを別のメイドに取られたんだ。お前も何か奉仕しないと気がきではないだろう?」
「い、いえ・・・そんな事は・・・。」
それは正治の本心だったが、恭平がそんな事で許す筈も無かった。
「まぁ無理するな。お前は今日から入った新入りメイドだからな。ご主人様にご奉仕したくて仕方が無い。そうだろう?」
「い・・・いえ・・・・。」
「何だ!?ハッキリ言え!」
正治の小さな抗いの言葉は恭平の怒鳴り声によってかき消された。
「い・・いえ・・・奉仕・・・したいです・・・。」
恭平の怒気に押された正治は思わず、そう返事をしてしまった。
「そうかそうか、そんなに俺に奉仕したいんだな。」
恭平は笑って結衣を見た。
「おい、結衣。実に感心な新米メイドだな。折角だから夜まで待っておこうと思っていた奉仕をさせてやるか。」
結衣はクスクスと笑って言う。
「いい考えね。新米メイドの忠誠心を確かめるのには丁度良い機会だわ。」
何をさせられるのか分からず、怯える正治を恭平は傍にくる様に命じる。正治は膝をついたまま恭平の足下に近づいた。妻が憎き男の足の指を丁寧にしゃぶる音が正治の神経を逆なでる。
「じゃあ夫婦揃ってご奉仕してもらおうか。マノン、お前が奉仕するのはこれだ。」
恭平は面白くてたまらないといった表情でズボンのボタンを外すと、そのままチャックとトランクスをずり下げ、己の凶悪なペニスをあらわにした。
「あっ・・・あぁっ・・・・あぁっ!!・・・・」
自分が何に対して奉仕するかと言うことを悟り、正治の顔が真っ青になる。
「どうした?ご主人様のペニスに対して奉仕するのは、メイドとして一番の悦びだろうが?」
「ひっ!ひいっ!」
思わず後ずさりして逃げようとした正治の背中を結衣が押さえる。腰が抜けた彼は結衣の手で再び恭平の前に押しやられた。勃起こそしていないが、自分とは全く異なるズル剥けの赤黒いペニスを目の当たりにし、正治は震えが止まらなかった。
「ほら、遠慮する事はない。存分にしゃぶっていいんだぞ。」
恭平が指でペニスの根本をつかんで正治の頬を張る。男臭い匂いが鼻につき、正治はもう死にたい程の感覚に襲われた。
「どうした?それともこっちも未穂に舐めさせたいのか?」
その言葉は正治に少しだけ理性を取り戻させた。愛する妻がこの男のペニスを舐めるなんて考えたくもない光景だった。
「・・・・・分かった・・・。」
正治はそう小さく呟くと、目の前の男のものを恐る恐る手にとってみる。
「そうかそうか、その気になったか。じゃあしゃぶらせてやろう。もちろん俺が射精するまで許さないからな。ほら、さっさと咥えろ、この淫乱メイドがっ!」
「は、はいっ・・・」
正治は涙ながらに、その恭平のペニスに口を付けた。
「う、うえっ・・・」
生臭い匂いが口内に広がり、彼は嘔吐しそうになる。
「ははぁ、さてはフェラは初体験か。」
恭平が白々しく驚いた様な顔をする。
「しかしフェラ奉仕はメイドにとって基本的な事だ。これぐらい出来ないと話にならないぞ・・・おら!もっと口に含むんだよ!」
「ひゃいっ・・・」
正治は息を止めてその肉棒を喉の奥まで咥え込んだ。
「ご主人様、私もー。」
気が付けば隣では未穂が羨ましそうに自分を見ている。そういえば、何度か頼んだ事はあるが、未穂が自分に対しては決して『奉仕』してくれなかった事を正治は思い出した。
「お前は後からだ。今は亭主が男のチンコを舐めるところを見て楽しんでいるんだな。」
恭平の言葉に、未穂が拗ねた様に言う。
「ちょっと、正治ったら男のクセメイド服着て男のチンポ咥えちゃって・・・プライドってもんが無いの?言っておくけど、そのおちんちんは私のものなんだからね。」
以前では考えられない妻の口から飛び出す卑猥な言葉に正治は愕然とするが、目の前の現実からは逃げる事は出来なかった。『妻を正気に戻す為』彼は、同性のペニスを舐め続けた。
奪われた妻と俺の性04
「ご主人様、奥様、宜しくお願い致します。」
とうとう色違いのお揃いのメイド服に着替えさせられた正治と未穂は、二人の年下カップルの前に立たされ、恭しく頭を下げさせられた。
「いいざまだな。しかし、頭が高いんじゃねぇの?」
恭平がそう言ってソファの上で足を組む。
「・・・・くっ・・・申し訳ありません・・・。」
正治は屈辱を感じながらも、未穂と共に床に両手をついた。
「ご主人様、奥様・・・宜しくお願い致します・・・。」
二人は夫婦並んでリビングの床に頭を擦りつけた。
「おい結衣、未穂はいいとしてもこっちのメイドの方は『正治』じゃしらけるなぁ。」
満足したように正治の頭を踏みつけながら恭平が言った。
「そうね。これから奴隷女になるんだし、それらしい名前を考えてあげないとね。」
結衣が同調して笑いながら言った。
「そうね・・・まさはるだから・・・『マノン』なんてどうかしら?」
「なんだそりゃぁ・・・?」
恭平はしばらく考えてから大声で笑った。
「あっはっはっ。そうかそうか、ぴったりの名前だ。こりゃあいいな。」
正治の顔を上げさせると、恭平はにやりと笑って言った。
「おい、今日からお前の名前は『マノン』ちゃんだ。分かったか?」
「は、はい・・・・。」
逆らう訳にもいかず、正治は素直に頷いた。
「二代目マノンちゃんの誕生ね。」
結衣までもがそう言って爆笑する。不思議な顔をしている正治に恭平が言った。
「マノンっていうのはな、結衣が小学校の時に飼っていた愛犬らしいぜ。どうだ、お前もこれから未穂と共に牝犬になるんだから、ぴったりの名前だろう。あはははははっ!」
自分が牝犬と同じ名前を付けられた事に憤然とする正治だったが、それを口に出すわけにもいかずうな垂れるしかなかった。
「ほら、自己紹介してみろよ、可愛くなっ。」
恭平が土下座したままの正治を急かせた。
「あ・・・あのっ・・・ご主人様・・・・私は・・・マ、マノンです・・・。」
「あぁ?声がちいさくって聞こえねえよ。」
恭平は耳に手を当ててドスの効いた声で叫んだ。正治は仕方無く声を張り上げる。
「マ、マノンと申します!ご主人様、奥様、これから宜しくお願い致しますっ!」
「もっと丁寧に挨拶しろっ!」
「は、はいっ!!」
妻のまでどれだけ辱めるつもりだろう。正治は怒りを感じながらもその場は従うしか無い。
「マノンと申しますっ!新米の至らぬど、奴隷メイド・・・ですがっ・・・一生懸命・・・・ご主人様と奥様に・・・・ほ、奉仕させて頂きますので・・・宜しく・・・お願い・・・・・致しますっ・・・。」
「そうかそうか、良い心がけだ。よし、じゃあ早速オレの足を舐めてもらおうか。」
目の前に恭平のごつい足が差し出され、さすがの正治も戸惑うだけだった。
「どうした?・・・奉仕してくれるんじゃなかったのか?えっ?」
いくらなんでも女性の美しい足ならともかく、同性の汚らしい足など舐められる訳が無い。正治は突き出されるその足から思わず顔を背けた。
「ご主人様、私に舐めさせて下さいませっ!」
そう言って正治を押しのけたのは妻の未穂だった。
「や、やめろっ!」
妻が自分を庇ってくれた。まだ俺に愛情があるのだ。そう思って未穂を見た正治はすぐにそれが間違いである事に気が付く。
「ご主人様、こんな役に立たない奴隷は放っておいて、わたしにおしゃぶりさせて下さいませっ。」
そう言った未穂の目はトロンとしていた。妻がもう自分のものでは無く、目の前の憎い男のものだという事に、正治は今更ながら気が付かされた。
とうとう色違いのお揃いのメイド服に着替えさせられた正治と未穂は、二人の年下カップルの前に立たされ、恭しく頭を下げさせられた。
「いいざまだな。しかし、頭が高いんじゃねぇの?」
恭平がそう言ってソファの上で足を組む。
「・・・・くっ・・・申し訳ありません・・・。」
正治は屈辱を感じながらも、未穂と共に床に両手をついた。
「ご主人様、奥様・・・宜しくお願い致します・・・。」
二人は夫婦並んでリビングの床に頭を擦りつけた。
「おい結衣、未穂はいいとしてもこっちのメイドの方は『正治』じゃしらけるなぁ。」
満足したように正治の頭を踏みつけながら恭平が言った。
「そうね。これから奴隷女になるんだし、それらしい名前を考えてあげないとね。」
結衣が同調して笑いながら言った。
「そうね・・・まさはるだから・・・『マノン』なんてどうかしら?」
「なんだそりゃぁ・・・?」
恭平はしばらく考えてから大声で笑った。
「あっはっはっ。そうかそうか、ぴったりの名前だ。こりゃあいいな。」
正治の顔を上げさせると、恭平はにやりと笑って言った。
「おい、今日からお前の名前は『マノン』ちゃんだ。分かったか?」
「は、はい・・・・。」
逆らう訳にもいかず、正治は素直に頷いた。
「二代目マノンちゃんの誕生ね。」
結衣までもがそう言って爆笑する。不思議な顔をしている正治に恭平が言った。
「マノンっていうのはな、結衣が小学校の時に飼っていた愛犬らしいぜ。どうだ、お前もこれから未穂と共に牝犬になるんだから、ぴったりの名前だろう。あはははははっ!」
自分が牝犬と同じ名前を付けられた事に憤然とする正治だったが、それを口に出すわけにもいかずうな垂れるしかなかった。
「ほら、自己紹介してみろよ、可愛くなっ。」
恭平が土下座したままの正治を急かせた。
「あ・・・あのっ・・・ご主人様・・・・私は・・・マ、マノンです・・・。」
「あぁ?声がちいさくって聞こえねえよ。」
恭平は耳に手を当ててドスの効いた声で叫んだ。正治は仕方無く声を張り上げる。
「マ、マノンと申します!ご主人様、奥様、これから宜しくお願い致しますっ!」
「もっと丁寧に挨拶しろっ!」
「は、はいっ!!」
妻のまでどれだけ辱めるつもりだろう。正治は怒りを感じながらもその場は従うしか無い。
「マノンと申しますっ!新米の至らぬど、奴隷メイド・・・ですがっ・・・一生懸命・・・・ご主人様と奥様に・・・・ほ、奉仕させて頂きますので・・・宜しく・・・お願い・・・・・致しますっ・・・。」
「そうかそうか、良い心がけだ。よし、じゃあ早速オレの足を舐めてもらおうか。」
目の前に恭平のごつい足が差し出され、さすがの正治も戸惑うだけだった。
「どうした?・・・奉仕してくれるんじゃなかったのか?えっ?」
いくらなんでも女性の美しい足ならともかく、同性の汚らしい足など舐められる訳が無い。正治は突き出されるその足から思わず顔を背けた。
「ご主人様、私に舐めさせて下さいませっ!」
そう言って正治を押しのけたのは妻の未穂だった。
「や、やめろっ!」
妻が自分を庇ってくれた。まだ俺に愛情があるのだ。そう思って未穂を見た正治はすぐにそれが間違いである事に気が付く。
「ご主人様、こんな役に立たない奴隷は放っておいて、わたしにおしゃぶりさせて下さいませっ。」
そう言った未穂の目はトロンとしていた。妻がもう自分のものでは無く、目の前の憎い男のものだという事に、正治は今更ながら気が付かされた。
奪われた妻と俺の性03
「さあ、着替えてもらおうかな。もちろんここでな。」
恭平は更に結衣から受け取った下着を正治と未穂に投げつけた。
「くっ・・・・下着まで・・・・女物を着けろと・・・・。」
それはメイド服と合わせたかの様な、水色とピンク色の鮮やかなブラとショーツだった。どちらにもたっぷりのレースとフリルがふんだんにあしらわれている。
「ほら、遠慮無く着ていいんだぞ。代金は後でお前の給料から天引きしておいてやるからな。」
正治はその慣れない下着を震える手で見つめた。どうやら妻に渡されたものと違い、自分に渡されたものはほとんど胸が無いものの様だ。内側のタグには『A65』と書かれている。
「あははは。まるで中学生の着る様なサイズのブラだが、今のお前にはぴったりだろう。まあ、いずれ未穂のと同じサイズのが必要になるかもしれないがな。」
その言葉は正治の耳には届かなかった。
「ほら!早く着替えろと言っているだろう!」
恭平の怒鳴り声に、正治も未穂も慌てて立ち上がると仕方無く着ていた部屋着を脱ぎだす。
「あははは、夫婦でストリップね。」
年端もいかない娘になじられながら、夫婦は若い二人のカップルの前で全裸となった。
「いい格好だな。二人とも。」
恭平は満足げに二人の姿を見渡すと、残酷な言葉を吐いた。
「ご主人様の前で恥ずかしがる事は無い。手は太股に付けて直立しろ。」
「で・・・でも・・・。」
夫婦は同時に言ったが、許してくれる様な恭平では無い。
「何度も言わせるな。結衣、それでケツを叩いてやれ。」
恭平が結衣に布団叩きを渡す。
「へっへー♪」
結衣は楽しげに未穂の後ろに回り込んだ。
「未穂ちゃん、恭平君の言うことは素直に聞かないと・・・・」
結衣は未穂の尻に布団叩きを振り下ろす。
「駄目じゅじゃない!」
「きゃーあっ!!」
『パシン』という乾いた音がリビングに響き渡る。
「ご、ごめんなさい・・・・。」
予想以上のその痛みに未穂は思わずそう口走っていた。
「んふふ、意外と素直じゃない。旦那さんはどうかな?」
「や、やめろ・・・」
正治は後ずさるが、素っ裸という状態では無様この上無い。結衣は背中を向けた恭平の尻を力任せに叩いた。
「ぎゃーっ!!」
まるで飛び上がる様な格好で悲鳴を上げた正治の尻を、結衣は続けざまに殴打する。
「ひーっ!!い、いたいーっ!!やめて、やめてくれーっ!!」
みるみる間に正治の尻は真っ赤になってしまった。
「どう?素直になった?」
息も切らさずにそう言って笑う結衣の足下に正治は、まるで土下座する様に這いつくばった。
「は、はい・・・も、申し訳ありませんでした・・・ご主人様・・・。」
この瞬間、正治は精神的にも肉体的にも奴隷契約書のサインをしてしまった。
「よし、もう一度立ってみろ。」
今度は正治は前を隠すことなく立ち上がった。
その股間を見て、恭平と結衣は笑いを堪えきれなかった。
「お前、よくそんなのでSEXしていたな。」
正治の股の間には、まだすっぽりと皮を被ったままの親指程度の物体が、申し訳なさそうにぶら下がっていたのだ。
「ねっ、私もホテルで見た時は驚いちゃったわ。だって、私の五歳の甥っ子よりちっちゃいんだもん。」
結衣が布団叩きで、正治のペニスを弄びながら高らかに笑った。
恭平は更に結衣から受け取った下着を正治と未穂に投げつけた。
「くっ・・・・下着まで・・・・女物を着けろと・・・・。」
それはメイド服と合わせたかの様な、水色とピンク色の鮮やかなブラとショーツだった。どちらにもたっぷりのレースとフリルがふんだんにあしらわれている。
「ほら、遠慮無く着ていいんだぞ。代金は後でお前の給料から天引きしておいてやるからな。」
正治はその慣れない下着を震える手で見つめた。どうやら妻に渡されたものと違い、自分に渡されたものはほとんど胸が無いものの様だ。内側のタグには『A65』と書かれている。
「あははは。まるで中学生の着る様なサイズのブラだが、今のお前にはぴったりだろう。まあ、いずれ未穂のと同じサイズのが必要になるかもしれないがな。」
その言葉は正治の耳には届かなかった。
「ほら!早く着替えろと言っているだろう!」
恭平の怒鳴り声に、正治も未穂も慌てて立ち上がると仕方無く着ていた部屋着を脱ぎだす。
「あははは、夫婦でストリップね。」
年端もいかない娘になじられながら、夫婦は若い二人のカップルの前で全裸となった。
「いい格好だな。二人とも。」
恭平は満足げに二人の姿を見渡すと、残酷な言葉を吐いた。
「ご主人様の前で恥ずかしがる事は無い。手は太股に付けて直立しろ。」
「で・・・でも・・・。」
夫婦は同時に言ったが、許してくれる様な恭平では無い。
「何度も言わせるな。結衣、それでケツを叩いてやれ。」
恭平が結衣に布団叩きを渡す。
「へっへー♪」
結衣は楽しげに未穂の後ろに回り込んだ。
「未穂ちゃん、恭平君の言うことは素直に聞かないと・・・・」
結衣は未穂の尻に布団叩きを振り下ろす。
「駄目じゅじゃない!」
「きゃーあっ!!」
『パシン』という乾いた音がリビングに響き渡る。
「ご、ごめんなさい・・・・。」
予想以上のその痛みに未穂は思わずそう口走っていた。
「んふふ、意外と素直じゃない。旦那さんはどうかな?」
「や、やめろ・・・」
正治は後ずさるが、素っ裸という状態では無様この上無い。結衣は背中を向けた恭平の尻を力任せに叩いた。
「ぎゃーっ!!」
まるで飛び上がる様な格好で悲鳴を上げた正治の尻を、結衣は続けざまに殴打する。
「ひーっ!!い、いたいーっ!!やめて、やめてくれーっ!!」
みるみる間に正治の尻は真っ赤になってしまった。
「どう?素直になった?」
息も切らさずにそう言って笑う結衣の足下に正治は、まるで土下座する様に這いつくばった。
「は、はい・・・も、申し訳ありませんでした・・・ご主人様・・・。」
この瞬間、正治は精神的にも肉体的にも奴隷契約書のサインをしてしまった。
「よし、もう一度立ってみろ。」
今度は正治は前を隠すことなく立ち上がった。
その股間を見て、恭平と結衣は笑いを堪えきれなかった。
「お前、よくそんなのでSEXしていたな。」
正治の股の間には、まだすっぽりと皮を被ったままの親指程度の物体が、申し訳なさそうにぶら下がっていたのだ。
「ねっ、私もホテルで見た時は驚いちゃったわ。だって、私の五歳の甥っ子よりちっちゃいんだもん。」
結衣が布団叩きで、正治のペニスを弄びながら高らかに笑った。
奪われた妻と俺の性02
その夜、勝ち誇った表情で帰宅した恭平に正治は何も言うことが出来なかった。
謀略にかけられたと言っても、実際に浮気といえる行為を行ったのは自分だし、未穂の心が既に自分に無い事も明白だった。
恭平の話によると彼と結衣は現在恋仲にあり、結婚を考えているという。しかしお互いの浪費癖で結婚資金もなければ新居を用意する金も無い。そこで、この部屋を二人に譲与すれば何事も無かった事にしてやろうというのだ。
妻はその夜一言も口を聞いてくれず、正治の夜は後悔のうちに明けていった。
そして次の日、恭平と結衣が少しの荷物を持ってやってきた。
「はーい、正治先輩久しぶりぃ♪」
結衣は悪びれもせず軽い挨拶を交わす。精一杯の凄みを効かせて結衣を睨んだ正治だったが、彼女には全く罪悪感というものは無い様だった。
「へぇっ!なかなか広い部屋じゃん。うん、私この部屋でいいよ。」
結衣は未穂の使っていた部屋にずけずけと入ると荷物を放り出す。
「じゃあ俺は隣の寝室に住ませてもらおうかな。」
恭平は夫婦の神聖な部屋である寝室に踏み込むと、遠慮無くクローゼットを開く。
「おいおい、こんなにいやらしいランジェリー揃えて何をしてたんですか、先輩?」
恭平はクローゼットに並んだ未穂のベビードールを取りだして下品な笑いを浮かべた。
「や、やめろ!勝手に・・・!」
恭平の手からそれを奪い取り、正治は慌ててクローゼットを閉じる。それは正治のリクエストで、夜の営みの際に未穂に着てもらっていたもので、正治にとって恥以外の何物でもなかった。
「おやおや、こっちが優しくしてるから、まだ自分の立場が分かってない様ですねぇ。」
恭平はニヤニヤと笑ったまま、正治の胸ぐらをつかみ上げた。
「今日からは俺達がご主人様で、お前らは奴隷だ。ゆっくりとその事を分からせてやろう・・・結衣!」
「大声出してどうしたの、恭平?」
隣室からやってきた結衣は既に部屋着に着替えていた。恭平は凄い力で正治を床に投げ倒すと、結衣に向かって言った。
「例の服持って来ただろう?それをこいつらに着せてやれ。」
そして、結衣が用意したその衣装を見て、正治はおろか未穂まで絶句してしまった。
「どうした、妙な顔をして?昨日言っただろ、お前らにはメイドになってもらうってな。」
恭平の言葉通り、二人の目の前に並べられたのは紛れもない『メイド服』だった。
「ま、まさか・・・これを・・・俺に・・・。」
信じられないと言った口調で呟く正治に恭平は冷たく言い放つ。
「他にどういう意味があると思う?」
「み、未穂はともかく・・・お、俺は男だぞ?お前正気か?」
その瞬間、恭平の平手打ちが正治の頬に飛ぶ。
「うぐうっ!」
「口の利き方に気を付けろ。次は握って殴るぞ。」
「す・・・すいません・・・・。」
昨日の傷も癒えない状態で殴られた正治はすっかり大人しくなってしまった。
「ねぇ、早く着てみせてよぉ。メイド喫茶でバイトしてる友達に無理言って用意してもらったんだからさぁ。」
後ろでそのやりとりをおかしそうに見ていた結衣がそう言って笑った。
「ほら、結衣もああ言ってるだろ。さっさと着替えてみせてよ、未穂ちゃんに、正治ちゃん♪あはははは!」
「く、くそっ・・・・」
床を拳で叩いて悔しがる正治だったが、もちろんそんな事で事態が好転する筈もない。
「そうだな、未穂にはこっちの水色のを・・・正治、お前はこっちの着てみせろ。」
正治に指示されたのは未穂と同じデザインだが、パステルカラーのピンク色に染められたフリルとレースたっぷりのメイド服だ。男の自分がメイド服を着るなどという信じられない状況に正治は目が回る思いだった。
「どうした?未穂を取り戻したいんじゃないのか?俺は一年間言うことを聞いたら自由にしてやってもいいと言ってるんだぜ。」
恭平の出したもう一つの条件は『一年間自分たちと一緒に住むこと』だった。彼らはその間、恭平の稼ぎを貪り、未穂をメイドとして扱うつもりだった。しかし正治にとっての誤算は、自分までもがメイド扱いされる事だった。
「ど、どうしてここまで・・・・。」
正治の問いに恭平はニヤリと笑って答える。
「ただ俺達がそういうのが好きなだけだよ。」
恭平のその言葉に正治は背筋が凍った。
謀略にかけられたと言っても、実際に浮気といえる行為を行ったのは自分だし、未穂の心が既に自分に無い事も明白だった。
恭平の話によると彼と結衣は現在恋仲にあり、結婚を考えているという。しかしお互いの浪費癖で結婚資金もなければ新居を用意する金も無い。そこで、この部屋を二人に譲与すれば何事も無かった事にしてやろうというのだ。
妻はその夜一言も口を聞いてくれず、正治の夜は後悔のうちに明けていった。
そして次の日、恭平と結衣が少しの荷物を持ってやってきた。
「はーい、正治先輩久しぶりぃ♪」
結衣は悪びれもせず軽い挨拶を交わす。精一杯の凄みを効かせて結衣を睨んだ正治だったが、彼女には全く罪悪感というものは無い様だった。
「へぇっ!なかなか広い部屋じゃん。うん、私この部屋でいいよ。」
結衣は未穂の使っていた部屋にずけずけと入ると荷物を放り出す。
「じゃあ俺は隣の寝室に住ませてもらおうかな。」
恭平は夫婦の神聖な部屋である寝室に踏み込むと、遠慮無くクローゼットを開く。
「おいおい、こんなにいやらしいランジェリー揃えて何をしてたんですか、先輩?」
恭平はクローゼットに並んだ未穂のベビードールを取りだして下品な笑いを浮かべた。
「や、やめろ!勝手に・・・!」
恭平の手からそれを奪い取り、正治は慌ててクローゼットを閉じる。それは正治のリクエストで、夜の営みの際に未穂に着てもらっていたもので、正治にとって恥以外の何物でもなかった。
「おやおや、こっちが優しくしてるから、まだ自分の立場が分かってない様ですねぇ。」
恭平はニヤニヤと笑ったまま、正治の胸ぐらをつかみ上げた。
「今日からは俺達がご主人様で、お前らは奴隷だ。ゆっくりとその事を分からせてやろう・・・結衣!」
「大声出してどうしたの、恭平?」
隣室からやってきた結衣は既に部屋着に着替えていた。恭平は凄い力で正治を床に投げ倒すと、結衣に向かって言った。
「例の服持って来ただろう?それをこいつらに着せてやれ。」
そして、結衣が用意したその衣装を見て、正治はおろか未穂まで絶句してしまった。
「どうした、妙な顔をして?昨日言っただろ、お前らにはメイドになってもらうってな。」
恭平の言葉通り、二人の目の前に並べられたのは紛れもない『メイド服』だった。
「ま、まさか・・・これを・・・俺に・・・。」
信じられないと言った口調で呟く正治に恭平は冷たく言い放つ。
「他にどういう意味があると思う?」
「み、未穂はともかく・・・お、俺は男だぞ?お前正気か?」
その瞬間、恭平の平手打ちが正治の頬に飛ぶ。
「うぐうっ!」
「口の利き方に気を付けろ。次は握って殴るぞ。」
「す・・・すいません・・・・。」
昨日の傷も癒えない状態で殴られた正治はすっかり大人しくなってしまった。
「ねぇ、早く着てみせてよぉ。メイド喫茶でバイトしてる友達に無理言って用意してもらったんだからさぁ。」
後ろでそのやりとりをおかしそうに見ていた結衣がそう言って笑った。
「ほら、結衣もああ言ってるだろ。さっさと着替えてみせてよ、未穂ちゃんに、正治ちゃん♪あはははは!」
「く、くそっ・・・・」
床を拳で叩いて悔しがる正治だったが、もちろんそんな事で事態が好転する筈もない。
「そうだな、未穂にはこっちの水色のを・・・正治、お前はこっちの着てみせろ。」
正治に指示されたのは未穂と同じデザインだが、パステルカラーのピンク色に染められたフリルとレースたっぷりのメイド服だ。男の自分がメイド服を着るなどという信じられない状況に正治は目が回る思いだった。
「どうした?未穂を取り戻したいんじゃないのか?俺は一年間言うことを聞いたら自由にしてやってもいいと言ってるんだぜ。」
恭平の出したもう一つの条件は『一年間自分たちと一緒に住むこと』だった。彼らはその間、恭平の稼ぎを貪り、未穂をメイドとして扱うつもりだった。しかし正治にとっての誤算は、自分までもがメイド扱いされる事だった。
「ど、どうしてここまで・・・・。」
正治の問いに恭平はニヤリと笑って答える。
「ただ俺達がそういうのが好きなだけだよ。」
恭平のその言葉に正治は背筋が凍った。
奪われた妻と俺の性01
その日、森川正治がいつもと同じ様に自宅であるマンションに帰った時、珍しく妻である未穂は出迎えてくれなかった。
「ただいまぁ!」
異変を感じた正治は靴を脱ぎながら大声を出したが返事は無い。
買い物にでも行っているのだろうか?しかしいつもこの時間にはもう夕食はほぼ出来上がっているのが常である。几帳面である未穂がメールで連絡もせずに家を空けるとはおおよそ考えられなかった。
「未穂!」
何か悪い事があったに違いないと感じた正治はリビングに駆け込んだ。
しかしそこには未穂の姿は無かった。台所を見ると料理の途中であった事がありありと見て取れる。真っ青になった正治は続いて未穂の部屋、自身の部屋を覗いたが彼女の姿は見あたらなかった。
「そうか、具合が悪くて寝ているに違いない。」
最後にそう思い当たった正治は少し気を取り直して、寝室のドアを開けた。
「未穂、大丈夫かい?」
しかし寝室の光景は正治を絶句させた。
「あっ・・・あなたっ・・・だめっ・・・」
未穂は犬の様に四つん這いでベッドに寝かされ、背中から男に犯されていた。
「やぁお帰りなさい、先輩。」
そして、あろうことか妻を犯していたのは正治の後輩である田井中恭平であった。
「な、何をしている・・・。」
あまりの出来事にしばし呆然となった正治は、ようやくそんな言葉を絞り出す。
「何って・・・セックスじゃないですか?知りません?」
恭平は腰を振るのも止めずにそう言った。一方の未穂も逃げ出そうともせずに、彼のモノを受け入れ続けていた。
「き・・・きさまっ!!」
我に返った正治は恭平につかみかかる。しかし、一瞬早く恭平の右フックが正治の左の頬を直撃した。
「舐めない方がいいッスよ、俺大学時代ボクシング部でしたから。さっ・・・続き、続き・・・」
床に倒れ込んだ正治を放っておき、恭平は再度未穂の膣内にペニスを突き刺した。
「あぁっ・・すっ・・・凄いっ!・・・」
未穂の喘ぎ声が寝室にこだまする。
「聞いたか正治先輩?奥さんはこんなに太いチンポは味わった事無いってよ。今までどんなチンポでセックスしてたんだ?まさか剥けてもいないなんて言わないだろうな?おっ!・・・よしっ・・・ほらっ・・・出すぞっ!!」
「だ、だめえっ!!」
「や、やめろっ!!」
二人の悲鳴が響く中、恭平は人妻の膣内に自らの精液をぶちまけてしまった。
「さて、話をしてあげましょうか先輩。」
すっかり満足し終えた表情で恭平はベッドの脇に座って、まだ床下に倒れ込んでいる正治に話しかけた。
「これ、みて下さいよ。」
恭平は正治の目の前に一枚の写真を落とす。
「あっ!・・・・・」
そこには正治と若い女性が手を組んで歩く姿が映っていた。その結衣という女性は恭平と同期で彼女も正治の後輩だった。
「こ、これはっ!!」
「言い訳無用っすよ。これ見せたら奥さん泣いちゃってねぇ。」
「きさまぁっ!!」
「あれ、逆切れっすか?先に浮気したのはどっちなのかな?あーあ、こんなに若くて可愛い奥さんがいるのにどーして浮気なんかするかねー。」
恭平の言うとおり未穂は恭平よりも若く美しかった。そしてまだ結婚後一年も立っていない彼女を正治は真剣に愛していた。
「あ・・・あれは・・・。」
正治はあの日の事を思い出していた。後輩の女の子から『相談がある』と言われれば男として悪い気はしない。会社帰りの飲み屋、二軒目のバー、泥酔した後のホテル・・・。正治にとって天国でも悪夢でもあったその出来事ははっきりと脳裏に焼き付いていた。
「それでね、奥さん離婚も考えてるんだって。」
「ほ、ほんとか!?」
状況も忘れ、正治は未穂に詰問した。彼女は涙を流しながら黙って頷いた。
「く、くそっ!」
自らの軽率な行為と、恭平さえばらさなければという怒りで正治の頭はおかしくなりそうだった。
「と、とにかくお前はもう出て行け!関係ないだろう!」
ようやく立ち上がった正治は恭平を指さして叫んだ。
「いえいえ、もうそういう訳にもいかなくてね・・・・。」
恭平は未穂の顔をじっと見た。
「い、行かないで・・・・・。」
未穂が彼に向かってそう言った時、正治は自らの敗北を悟った。
「さて、そういう訳なんですが、僕も無理に幸せな家庭を崩壊させるのは本意じゃない。」
恭平は立ち上がって、脱ぎ散らかした洋服を身につけながら語り出した。
「一つ条件を付ければ家庭はこのままにしておいてあげましょう。」
「な、なんだと?」
「言ってる通りですよ。その条件が飲めればね。」
「無かった事にしてくれると言うんだな・・・・。」
時間が立てば未穂の気持ちも取り戻す事ができるだろうという自身を持って、正治はそう尋ねた。
「えぇ、その通りです。」
「では、その条件を話してもらおうか。未穂といられるのならどんな条件でも飲んでみせよう。」
少々芝居がかった言い回しで、正治は妻の視線を気にしながらそう言い張った。
「俺と結衣がここで暮らすから、あんたたち夫婦には俺達のメイドになってもらおうか。それが条件だ。」
『嵌められた・・・・・』正治はようやく全てが計画されたことだと気が付いた。
「ただいまぁ!」
異変を感じた正治は靴を脱ぎながら大声を出したが返事は無い。
買い物にでも行っているのだろうか?しかしいつもこの時間にはもう夕食はほぼ出来上がっているのが常である。几帳面である未穂がメールで連絡もせずに家を空けるとはおおよそ考えられなかった。
「未穂!」
何か悪い事があったに違いないと感じた正治はリビングに駆け込んだ。
しかしそこには未穂の姿は無かった。台所を見ると料理の途中であった事がありありと見て取れる。真っ青になった正治は続いて未穂の部屋、自身の部屋を覗いたが彼女の姿は見あたらなかった。
「そうか、具合が悪くて寝ているに違いない。」
最後にそう思い当たった正治は少し気を取り直して、寝室のドアを開けた。
「未穂、大丈夫かい?」
しかし寝室の光景は正治を絶句させた。
「あっ・・・あなたっ・・・だめっ・・・」
未穂は犬の様に四つん這いでベッドに寝かされ、背中から男に犯されていた。
「やぁお帰りなさい、先輩。」
そして、あろうことか妻を犯していたのは正治の後輩である田井中恭平であった。
「な、何をしている・・・。」
あまりの出来事にしばし呆然となった正治は、ようやくそんな言葉を絞り出す。
「何って・・・セックスじゃないですか?知りません?」
恭平は腰を振るのも止めずにそう言った。一方の未穂も逃げ出そうともせずに、彼のモノを受け入れ続けていた。
「き・・・きさまっ!!」
我に返った正治は恭平につかみかかる。しかし、一瞬早く恭平の右フックが正治の左の頬を直撃した。
「舐めない方がいいッスよ、俺大学時代ボクシング部でしたから。さっ・・・続き、続き・・・」
床に倒れ込んだ正治を放っておき、恭平は再度未穂の膣内にペニスを突き刺した。
「あぁっ・・すっ・・・凄いっ!・・・」
未穂の喘ぎ声が寝室にこだまする。
「聞いたか正治先輩?奥さんはこんなに太いチンポは味わった事無いってよ。今までどんなチンポでセックスしてたんだ?まさか剥けてもいないなんて言わないだろうな?おっ!・・・よしっ・・・ほらっ・・・出すぞっ!!」
「だ、だめえっ!!」
「や、やめろっ!!」
二人の悲鳴が響く中、恭平は人妻の膣内に自らの精液をぶちまけてしまった。
「さて、話をしてあげましょうか先輩。」
すっかり満足し終えた表情で恭平はベッドの脇に座って、まだ床下に倒れ込んでいる正治に話しかけた。
「これ、みて下さいよ。」
恭平は正治の目の前に一枚の写真を落とす。
「あっ!・・・・・」
そこには正治と若い女性が手を組んで歩く姿が映っていた。その結衣という女性は恭平と同期で彼女も正治の後輩だった。
「こ、これはっ!!」
「言い訳無用っすよ。これ見せたら奥さん泣いちゃってねぇ。」
「きさまぁっ!!」
「あれ、逆切れっすか?先に浮気したのはどっちなのかな?あーあ、こんなに若くて可愛い奥さんがいるのにどーして浮気なんかするかねー。」
恭平の言うとおり未穂は恭平よりも若く美しかった。そしてまだ結婚後一年も立っていない彼女を正治は真剣に愛していた。
「あ・・・あれは・・・。」
正治はあの日の事を思い出していた。後輩の女の子から『相談がある』と言われれば男として悪い気はしない。会社帰りの飲み屋、二軒目のバー、泥酔した後のホテル・・・。正治にとって天国でも悪夢でもあったその出来事ははっきりと脳裏に焼き付いていた。
「それでね、奥さん離婚も考えてるんだって。」
「ほ、ほんとか!?」
状況も忘れ、正治は未穂に詰問した。彼女は涙を流しながら黙って頷いた。
「く、くそっ!」
自らの軽率な行為と、恭平さえばらさなければという怒りで正治の頭はおかしくなりそうだった。
「と、とにかくお前はもう出て行け!関係ないだろう!」
ようやく立ち上がった正治は恭平を指さして叫んだ。
「いえいえ、もうそういう訳にもいかなくてね・・・・。」
恭平は未穂の顔をじっと見た。
「い、行かないで・・・・・。」
未穂が彼に向かってそう言った時、正治は自らの敗北を悟った。
「さて、そういう訳なんですが、僕も無理に幸せな家庭を崩壊させるのは本意じゃない。」
恭平は立ち上がって、脱ぎ散らかした洋服を身につけながら語り出した。
「一つ条件を付ければ家庭はこのままにしておいてあげましょう。」
「な、なんだと?」
「言ってる通りですよ。その条件が飲めればね。」
「無かった事にしてくれると言うんだな・・・・。」
時間が立てば未穂の気持ちも取り戻す事ができるだろうという自身を持って、正治はそう尋ねた。
「えぇ、その通りです。」
「では、その条件を話してもらおうか。未穂といられるのならどんな条件でも飲んでみせよう。」
少々芝居がかった言い回しで、正治は妻の視線を気にしながらそう言い張った。
「俺と結衣がここで暮らすから、あんたたち夫婦には俺達のメイドになってもらおうか。それが条件だ。」
『嵌められた・・・・・』正治はようやく全てが計画されたことだと気が付いた。
ただいまです
予定より遅くなって申し訳ありません。
とりあえず復活報告をさせて頂きます。
コメント下さった方申し訳ありませんでした。
年明け後、しばらくしてから更新再開予定のつもりですので宜しくお願いします。
とりあえず復活報告をさせて頂きます。
コメント下さった方申し訳ありませんでした。
年明け後、しばらくしてから更新再開予定のつもりですので宜しくお願いします。
休載のお知らせ
更新滞って申し訳ありません。
諸事情によりましてしばらく休載させて頂きます。
秋頃の更新復活を予定しておりますので、またお会いできるのを楽しみにお待ちしております。
wind様コメントありがとうございました。初めてのコメントで感激しております。上記の様な訳ですので申し訳ありませんが続きはもうしばらくお待ち下さいませ。
諸事情によりましてしばらく休載させて頂きます。
秋頃の更新復活を予定しておりますので、またお会いできるのを楽しみにお待ちしております。
wind様コメントありがとうございました。初めてのコメントで感激しております。上記の様な訳ですので申し訳ありませんが続きはもうしばらくお待ち下さいませ。
娘の妻にされました11
「う、うえーっ・・・」
男の亀頭からカウパーが染み出し、その苦い臭いに秋人は吐き気を催した。
「うえっ!」
思わず口を離してしまった秋人の胸のリボンを男は乱暴につかむ。
「おいおい、じらすのはナシだろ。」
彼はそう言って無理矢理秋人の口内にいきり立ったペニスを押し込んだ。今度は秋人も我慢せざるを得ない。彼は嘔吐感と闘いながら男のものを必死に舐め続けた。
「しかし、課長さん。こんなことさせて大丈夫なんですか?」
男は股の間に秋人を挟みながら訪ねる。
「えぇ、この娘は根っからの淫乱でね。ときどきそうやってチンポを咥えさせてやらないと、だれかれ構わず男と見れば『フェラさせて!』なんて言い出すから私も困ってるんですよ。」
「んんんっ!」
秋人は否定しようとするが、男のものから口を離すわけにもいかず、それはくぐもった音にしかならなかった。
「そうですか。そのわりには稚拙だが・・・おら、もっと舌を転がせ!お前も感じてるんだろうが!」
男は足で秋人の制服のスカートを捲り上げると、靴の裏で股の間を踏みつける。
「う、うんんっ!」
パンティの上から股間を踏みつけられるという屈辱にも秋人は声さえも上げられない。
「ほらっ、秋奈君。ちんぽを咥えさせて頂いたお礼にお尻を振りたまえ。」
課長がとんでもないことを言い出したが秋人は逆らう訳にはいかなかった。
「ひゃいっ・・・」
彼は男のペニスを咥えたままの姿勢で四つん這いになると、すっかりと大きくなったお尻を左右に振った。その滑稽な仕草に課長と男はニヤニヤと笑った。
「折角だからお尻も見せなさい。」
課長は秋人のスカートを捲り、ショーツを下ろす。生白い臀部があらわになるが、秋人はそれを振り続けて媚びを売るしかなかった。
「課長さん、そっちの方はダメなんですか?」
不意に男が尋ねた。
「いえいえ、最初だからお口で奉仕させたまでです。もちろんご自由におつかい下さい。なにせ、この娘の穴という穴は私の管理下にありますから。」
課長はそう言って、無理矢理秋人の尻を男の方に向ける。
「ああっ・・・やめてっ・・・」
秋人の小さな叫びは二人の耳には届かなかった。
「い、いやーっ!!」
次の瞬間、男の熱くいきり立ったペニスが秋人の膣に挿入された。
「あ・・・あぁっ・・・」
ついに同性にお尻を犯されたショックに秋人は嗚咽ともいえる声を漏らした。
「ゆるゆるかと思ったらなかなかいいじゃないか・・・」
男がパシンと秋人の尻を叩いて言った。
「そ・・そんな・・・ああっ!・・・」
屈辱に胸を震わせながらも秋人は膣で感じてしまう。
「おらおら、気持ちいいかっ!?」
男が奥までペニスを挿入し、女性器を精嚢が刺激する感触に秋人は脳がとろけそうになるほどの快感を味わっていた。それはいくら「感じてはいけない」と頭で否定してもしきれないほどの女としての悦びだった。
「あ・・ああっ・・あぁあんっ!」
秋人はいつの間にか自然に腰を振っていた。
「とうとう本性が出たな、淫乱便所女め!どうだ自分で気持ちいいって言ってみろ!」
男のその様な侮辱の声も秋人はどこか他人事として聞いていた。
「あぁっ・・・あぁっ・・・おちんぽ・・・おちんぽが私のおまんこに・・・・おまんこ気持ちいいのっ!」
秋人は知らぬ間にそう口走っていた。
男の亀頭からカウパーが染み出し、その苦い臭いに秋人は吐き気を催した。
「うえっ!」
思わず口を離してしまった秋人の胸のリボンを男は乱暴につかむ。
「おいおい、じらすのはナシだろ。」
彼はそう言って無理矢理秋人の口内にいきり立ったペニスを押し込んだ。今度は秋人も我慢せざるを得ない。彼は嘔吐感と闘いながら男のものを必死に舐め続けた。
「しかし、課長さん。こんなことさせて大丈夫なんですか?」
男は股の間に秋人を挟みながら訪ねる。
「えぇ、この娘は根っからの淫乱でね。ときどきそうやってチンポを咥えさせてやらないと、だれかれ構わず男と見れば『フェラさせて!』なんて言い出すから私も困ってるんですよ。」
「んんんっ!」
秋人は否定しようとするが、男のものから口を離すわけにもいかず、それはくぐもった音にしかならなかった。
「そうですか。そのわりには稚拙だが・・・おら、もっと舌を転がせ!お前も感じてるんだろうが!」
男は足で秋人の制服のスカートを捲り上げると、靴の裏で股の間を踏みつける。
「う、うんんっ!」
パンティの上から股間を踏みつけられるという屈辱にも秋人は声さえも上げられない。
「ほらっ、秋奈君。ちんぽを咥えさせて頂いたお礼にお尻を振りたまえ。」
課長がとんでもないことを言い出したが秋人は逆らう訳にはいかなかった。
「ひゃいっ・・・」
彼は男のペニスを咥えたままの姿勢で四つん這いになると、すっかりと大きくなったお尻を左右に振った。その滑稽な仕草に課長と男はニヤニヤと笑った。
「折角だからお尻も見せなさい。」
課長は秋人のスカートを捲り、ショーツを下ろす。生白い臀部があらわになるが、秋人はそれを振り続けて媚びを売るしかなかった。
「課長さん、そっちの方はダメなんですか?」
不意に男が尋ねた。
「いえいえ、最初だからお口で奉仕させたまでです。もちろんご自由におつかい下さい。なにせ、この娘の穴という穴は私の管理下にありますから。」
課長はそう言って、無理矢理秋人の尻を男の方に向ける。
「ああっ・・・やめてっ・・・」
秋人の小さな叫びは二人の耳には届かなかった。
「い、いやーっ!!」
次の瞬間、男の熱くいきり立ったペニスが秋人の膣に挿入された。
「あ・・・あぁっ・・・」
ついに同性にお尻を犯されたショックに秋人は嗚咽ともいえる声を漏らした。
「ゆるゆるかと思ったらなかなかいいじゃないか・・・」
男がパシンと秋人の尻を叩いて言った。
「そ・・そんな・・・ああっ!・・・」
屈辱に胸を震わせながらも秋人は膣で感じてしまう。
「おらおら、気持ちいいかっ!?」
男が奥までペニスを挿入し、女性器を精嚢が刺激する感触に秋人は脳がとろけそうになるほどの快感を味わっていた。それはいくら「感じてはいけない」と頭で否定してもしきれないほどの女としての悦びだった。
「あ・・ああっ・・あぁあんっ!」
秋人はいつの間にか自然に腰を振っていた。
「とうとう本性が出たな、淫乱便所女め!どうだ自分で気持ちいいって言ってみろ!」
男のその様な侮辱の声も秋人はどこか他人事として聞いていた。
「あぁっ・・・あぁっ・・・おちんぽ・・・おちんぽが私のおまんこに・・・・おまんこ気持ちいいのっ!」
秋人は知らぬ間にそう口走っていた。
娘の妻にされました10
「秋奈君、ちょっと来たまえ。」
昼過ぎに秋人は課長室に呼ばれた。嫌な予感を抱えて入った課長室には先客が一人。秋人も知っている得意先の若い男性社員だった。
「紹介しよう。今日から入った秋奈君だ。」
男は秋人に会釈して頭を捻った。
「どこかでお会いしましたっけ?」
秋人が返事出来る筈も無い。代わりに課長が話し出した。
「今日は大口の契約をもらったんだよ。ほら、君からも頭を下げなさい。」
秋人はその場で頭を九十度下げた。
「そうじゃないだろ。君の頭の下げ方は!」
課長はそう言ってさりげなく課長室の扉を閉めると、秋人を男の前に跪かせて耳打ちする。
「そ・・そんな・・・。」
課長の言葉を聞いて震え上がる秋人に課長は冷たく言い放つ。
「なんだ?折角無理に職場復帰させてやった恩も忘れて逆らう気かね?」
「で、でも・・・あんまりです・・・。」
「そうか?じゃあ『旦那さん』に連絡するしかないなぁ。そうなればいよいよ君も本格的に家庭崩壊なんじゃないかね。」
それを聞いて青ざめた秋人は慌てて男に頭を下げた。
「ご、ご契約ありがとうございます。あ・・・秋奈に・・・」
秋人はソファに座っている男に土下座した。
「秋奈に、お礼のご・・・ご・・・奉仕をさせて下さいませ!」
「えっ?」
男は面食らった。目の前で初対面の女性が「ご奉仕させて下さいませ」と言っているのだ。無理もないだろう。
「まあまあ、あなたも若い男性なんだからこの娘の『ご奉仕』の意味ぐらい理解できるでしょう?」
課長はいやらしい声で言うと男の肩をさすった。
「さあ、始めなさい秋奈君」
課長の声には有無を言わさない脅迫が込められていた。
「失礼します。」
秋人はそう言って男のズボンのチャックを下ろす。
「ちょ、ちょっと!」
男はそう言いながら苦笑する。秋人は彼のズボンに手を入れると手探りでペニスを探り当て、丁寧にそれを外に導き出す。
「ご、ご立派ですね。」
そう言って秋人は顔を赤らめた。歩実から教育されたフェラチオの行儀がついつい出てしまったのだ。
「そうかい?」
しかしそれを聞いて「この女慣れている」と錯覚した男は秋人に『奉仕』させる事にためらいがなくなってしまった様だった。彼はソファにふんぞり返り秋人に指示を出す。
「丁寧にしゃぶれよ。」
「はっ、はいっ!」
旦那である歩実の調教は彼自身が思っていた以上に体に染みついてしまっている様だった。彼はそう返事すると、少し躊躇ったあと男のまだ垂れ下がっているペニスにしゃぶりついた。
「う・・・うぅ・・・っ・・・」
しかし、やはり歩実のディルドーとは訳が違う。口いっぱいに広がる若い男の臭いに秋人は嘔吐感を覚えた。
「どうした?随分慣れてる様子だったが、お口は処女なのか?」
「い、いえっ!」
あまり正体を探られては大変だ。秋人は思いきって再び男のものを口の奥まで咥え込んだ。
「たどたどしい感じもいいもんだな。」
みるみる間に男のものは秋人の口内で大きさを増していった。
昼過ぎに秋人は課長室に呼ばれた。嫌な予感を抱えて入った課長室には先客が一人。秋人も知っている得意先の若い男性社員だった。
「紹介しよう。今日から入った秋奈君だ。」
男は秋人に会釈して頭を捻った。
「どこかでお会いしましたっけ?」
秋人が返事出来る筈も無い。代わりに課長が話し出した。
「今日は大口の契約をもらったんだよ。ほら、君からも頭を下げなさい。」
秋人はその場で頭を九十度下げた。
「そうじゃないだろ。君の頭の下げ方は!」
課長はそう言ってさりげなく課長室の扉を閉めると、秋人を男の前に跪かせて耳打ちする。
「そ・・そんな・・・。」
課長の言葉を聞いて震え上がる秋人に課長は冷たく言い放つ。
「なんだ?折角無理に職場復帰させてやった恩も忘れて逆らう気かね?」
「で、でも・・・あんまりです・・・。」
「そうか?じゃあ『旦那さん』に連絡するしかないなぁ。そうなればいよいよ君も本格的に家庭崩壊なんじゃないかね。」
それを聞いて青ざめた秋人は慌てて男に頭を下げた。
「ご、ご契約ありがとうございます。あ・・・秋奈に・・・」
秋人はソファに座っている男に土下座した。
「秋奈に、お礼のご・・・ご・・・奉仕をさせて下さいませ!」
「えっ?」
男は面食らった。目の前で初対面の女性が「ご奉仕させて下さいませ」と言っているのだ。無理もないだろう。
「まあまあ、あなたも若い男性なんだからこの娘の『ご奉仕』の意味ぐらい理解できるでしょう?」
課長はいやらしい声で言うと男の肩をさすった。
「さあ、始めなさい秋奈君」
課長の声には有無を言わさない脅迫が込められていた。
「失礼します。」
秋人はそう言って男のズボンのチャックを下ろす。
「ちょ、ちょっと!」
男はそう言いながら苦笑する。秋人は彼のズボンに手を入れると手探りでペニスを探り当て、丁寧にそれを外に導き出す。
「ご、ご立派ですね。」
そう言って秋人は顔を赤らめた。歩実から教育されたフェラチオの行儀がついつい出てしまったのだ。
「そうかい?」
しかしそれを聞いて「この女慣れている」と錯覚した男は秋人に『奉仕』させる事にためらいがなくなってしまった様だった。彼はソファにふんぞり返り秋人に指示を出す。
「丁寧にしゃぶれよ。」
「はっ、はいっ!」
旦那である歩実の調教は彼自身が思っていた以上に体に染みついてしまっている様だった。彼はそう返事すると、少し躊躇ったあと男のまだ垂れ下がっているペニスにしゃぶりついた。
「う・・・うぅ・・・っ・・・」
しかし、やはり歩実のディルドーとは訳が違う。口いっぱいに広がる若い男の臭いに秋人は嘔吐感を覚えた。
「どうした?随分慣れてる様子だったが、お口は処女なのか?」
「い、いえっ!」
あまり正体を探られては大変だ。秋人は思いきって再び男のものを口の奥まで咥え込んだ。
「たどたどしい感じもいいもんだな。」
みるみる間に男のものは秋人の口内で大きさを増していった。
娘の妻にされました9
「初めまして。今日から入社しました雪平秋奈」です。
かつての同僚達の前でそう挨拶した秋人の足は屈辱で震えていた。
「まだ女になりたての小娘ですが、みなさまの足を引っ張らない様に精一杯奉仕させて頂きますので、どうか可愛がって下さいませ。きゃーっ!」
昨日歩実から指示された通りに挨拶した秋人の制服のスカートを山中課長が捲った。事情を知っている皆がクスクスと笑う。
「この通り、股間もつるつるだ。ほら、女になった証拠をみんなに見せないか!」
課長に言われた秋人は自ら両手で制服のスカートを捲ると、薄いレースのショーツを穿いた股間を前に突き出した。
「どうか・・・秋奈のいやらしい股間をご覧下さい・・・。」
課長は満足そうに頷く。
「皆も知っていると思うがこのように雪平係長は女性になって職場に復帰する事になった。しかし当分は新入社員、それも見習い扱いだ。皆もたっぷりと秋奈君を可愛がってあげたまえ。」
すっかりと女らしくなった秋人を見て数人の男性社員から口笛を吹く音が聞こえた。
「それから・・・」
課長は秋人の尻を撫でながら続けた。
「見て分かるとおもうが、秋奈君にはこの特製の制服を着てもらう。他の女子社員は可愛いからってうらやましがるんじゃないぞ。」
秋人の着せられている制服は他の女子社員とは異なるピンク色の特注制服だった。それは地味な紺色の一般女子制服とは違い、パステルピンクの生地のフレアのミニスカート、腰には大きな飾りリボンに襟にはフリルまであしらわれているまるで子供服のような可愛らしい制服だった。
「課長、そんな恥ずかしい制服私達着るのいやですよ。」
去年入ったばかりの女子社員が秋人を侮蔑の目で見ながら言った。
「秋奈、これコピーとってきなさい!」
業務が始まったが秋人の仕事は雑用しかなかった。
「おい秋奈、お茶いれてこい!」
「はいっ!」
しかし彼は屈辱に声を震わせながらも返事をして仕事を続けるしかない。まだ課長や年上の課員に命令されるのは耐えられたが、かつての部下やまだ高校を出たての新入女子社員にまで
「グズグズすんなよのろま!」
などと叱責されるのは耐え難い仕打ちだった。
それでも秋人は唯唯諾諾とその雑用を続けるしかない。彼は自分がかつて係長だった事を忘れようと一心不乱に仕事を続けるが、慣れない女性制服姿ではそれもおぼつかなかった。
「きゃっ!」
「も、申し訳ありません!」
汲んできたばかりのお茶を女子社員のデスクに零してしまった秋人は反射的に頭を下げた。
「なにしてるのよグズ!」
女子社員はすぐさま秋人の左頬を引っぱたいた。彼女は先月入社したばかりのまだ19歳の女の子だった。秋人が係長だった事を知らない為、彼女の秋人に対する仕打ちは容赦なかった。
「も・・・もうしわけ・・・ございません・・・。」
秋人はぐっと唇を噛んで頭を下げたが、その瞳からは涙がこぼれ落ちた。
「泣けばいいってもんじゃ無いでしょ?この濡れた書類どうするつもりよ!?」
女子社員は机の上でお茶に染まった書類を秋人の顔に押し当てる。べちゃっという音とともに彼の顔はお茶まみれになった。
「まったく・・・さっきからコピーさせても奇麗に出来ないし、お茶を入れさせたら先輩の机に零すし・・・あんた口で言っても分からないみたいね。」
女子社員は秋人の手をつかむと廊下に連れ出す。
「ほら、両手でこの濡れた書類持って乾くまでここに立ってなさい。『私は粗相をしてしまったので廊下に立たされているダメ社員です』って言いながらね。」
そう言って彼女は秋人のスカートのホックを外すとスカートをずり下げた。
「きゃっ!」
「女みたいな悲鳴あげないでよ。男なんだからパンツ見られるくらいどうってことないでしょ?ほら、さっさと声を出しなさい!」
「わっ・・・私は・・・粗相をしてしまったので・・廊下に立たされていまーすっ・・・」
「もっと、大きな声で!」
「わっ・・・私はぁ!粗相をしてしまったので!廊下に立たされていますっ!」
秋人はもう恥辱で真っ赤になっていた。
「時々見に来るからね。勝手にスカート穿いたら、今度は外に放り出すわよ!」
女子社員はそう吐き捨てて部屋に戻った。
大勢の社員達に嘲笑されながら秋人の謝罪の声出しは一時間以上も続いた。
かつての同僚達の前でそう挨拶した秋人の足は屈辱で震えていた。
「まだ女になりたての小娘ですが、みなさまの足を引っ張らない様に精一杯奉仕させて頂きますので、どうか可愛がって下さいませ。きゃーっ!」
昨日歩実から指示された通りに挨拶した秋人の制服のスカートを山中課長が捲った。事情を知っている皆がクスクスと笑う。
「この通り、股間もつるつるだ。ほら、女になった証拠をみんなに見せないか!」
課長に言われた秋人は自ら両手で制服のスカートを捲ると、薄いレースのショーツを穿いた股間を前に突き出した。
「どうか・・・秋奈のいやらしい股間をご覧下さい・・・。」
課長は満足そうに頷く。
「皆も知っていると思うがこのように雪平係長は女性になって職場に復帰する事になった。しかし当分は新入社員、それも見習い扱いだ。皆もたっぷりと秋奈君を可愛がってあげたまえ。」
すっかりと女らしくなった秋人を見て数人の男性社員から口笛を吹く音が聞こえた。
「それから・・・」
課長は秋人の尻を撫でながら続けた。
「見て分かるとおもうが、秋奈君にはこの特製の制服を着てもらう。他の女子社員は可愛いからってうらやましがるんじゃないぞ。」
秋人の着せられている制服は他の女子社員とは異なるピンク色の特注制服だった。それは地味な紺色の一般女子制服とは違い、パステルピンクの生地のフレアのミニスカート、腰には大きな飾りリボンに襟にはフリルまであしらわれているまるで子供服のような可愛らしい制服だった。
「課長、そんな恥ずかしい制服私達着るのいやですよ。」
去年入ったばかりの女子社員が秋人を侮蔑の目で見ながら言った。
「秋奈、これコピーとってきなさい!」
業務が始まったが秋人の仕事は雑用しかなかった。
「おい秋奈、お茶いれてこい!」
「はいっ!」
しかし彼は屈辱に声を震わせながらも返事をして仕事を続けるしかない。まだ課長や年上の課員に命令されるのは耐えられたが、かつての部下やまだ高校を出たての新入女子社員にまで
「グズグズすんなよのろま!」
などと叱責されるのは耐え難い仕打ちだった。
それでも秋人は唯唯諾諾とその雑用を続けるしかない。彼は自分がかつて係長だった事を忘れようと一心不乱に仕事を続けるが、慣れない女性制服姿ではそれもおぼつかなかった。
「きゃっ!」
「も、申し訳ありません!」
汲んできたばかりのお茶を女子社員のデスクに零してしまった秋人は反射的に頭を下げた。
「なにしてるのよグズ!」
女子社員はすぐさま秋人の左頬を引っぱたいた。彼女は先月入社したばかりのまだ19歳の女の子だった。秋人が係長だった事を知らない為、彼女の秋人に対する仕打ちは容赦なかった。
「も・・・もうしわけ・・・ございません・・・。」
秋人はぐっと唇を噛んで頭を下げたが、その瞳からは涙がこぼれ落ちた。
「泣けばいいってもんじゃ無いでしょ?この濡れた書類どうするつもりよ!?」
女子社員は机の上でお茶に染まった書類を秋人の顔に押し当てる。べちゃっという音とともに彼の顔はお茶まみれになった。
「まったく・・・さっきからコピーさせても奇麗に出来ないし、お茶を入れさせたら先輩の机に零すし・・・あんた口で言っても分からないみたいね。」
女子社員は秋人の手をつかむと廊下に連れ出す。
「ほら、両手でこの濡れた書類持って乾くまでここに立ってなさい。『私は粗相をしてしまったので廊下に立たされているダメ社員です』って言いながらね。」
そう言って彼女は秋人のスカートのホックを外すとスカートをずり下げた。
「きゃっ!」
「女みたいな悲鳴あげないでよ。男なんだからパンツ見られるくらいどうってことないでしょ?ほら、さっさと声を出しなさい!」
「わっ・・・私は・・・粗相をしてしまったので・・廊下に立たされていまーすっ・・・」
「もっと、大きな声で!」
「わっ・・・私はぁ!粗相をしてしまったので!廊下に立たされていますっ!」
秋人はもう恥辱で真っ赤になっていた。
「時々見に来るからね。勝手にスカート穿いたら、今度は外に放り出すわよ!」
女子社員はそう吐き捨てて部屋に戻った。
大勢の社員達に嘲笑されながら秋人の謝罪の声出しは一時間以上も続いた。
娘の妻にされました8
「ぴちゃっ・・・」
「じゅるっ・・・」
静かな歩実の部屋に卑猥な音が響き渡り、目を閉じても秋人は自分の行為の破廉恥さを確認させられずにはいられない。
「どう、俺のチンコうまいか?」
歩実が見下ろしながら尋ねる。秋人は上目遣いで従順な彼女を演じるしかなかった。
「う・・・うん・・・とってもおいしいわ・・・。」
細い声で言った秋人の怯える目を見て歩実は加虐心を刺激される。
「じゃあもっと丁寧に濡らすんだ。前みたいに痛い目にあいたくなかったらな。」
秋人はあの夜の事を思い出し恐怖に震える。彼は慌てて唾液を口に含むとディルドーに絡ませる。
「ふふふ、そんなに早く入れて欲しいのか。まだ中学生の癖に淫乱な娘だな。」
そう言いながら趣味は足で秋人の制服のスカートを捲ると、彼の股間に足の指を這わせた。
「あっ・・・だめっ・・・」
女性よりも感じる様にされた秋人は悲鳴の様な喘ぎ声を漏らす。
「ほらっ・・・口が留守だぞ!」
それを知っていて歩実は無理矢理彼の口にディルドーを押し込む。局部の快感に声を上げる事も出来ずに、秋人の恥部は段々と湿っていく。
「なんだ、お前嫌そうにしながらも濡れているじゃないか。」
歩実が秋人の股間から出た愛液で濡れた靴下を彼の顔に押しつける。
「ち・・違う・・・の・・・。」
「何が違うんだ?これはお前が出したものだろう?」
歩実が否定しても、その濡れた靴下から糸を引く液体は彼が感じてしまっている事実を如実に示していた。
「そろそろたまらないんじゃないか?」
歩実の言うとおりだった。口では否定しても体の機能は女にされた秋人にとって、長時間によるフェラチオ奉仕と足責めは彼の『女』を刺激するには十分過ぎた。
「じゃあベッドに四つん這いになれ。」
催眠術でもかけられた様に秋人は娘の指示でベッドに乗る。いけない事とは分かっていても体がそれを拒否出来なかった。
「自分でスカートを捲ってショーツを下ろせ。」
秋人は真っ赤になりながらも歩実の指示に従う。中学生の制服姿でベッドの上で尻を突き出してショーツを自ら下ろす姿はまるで本当に淫乱な小娘の様だった。
「処女のくせにこんなに濡らしやがって。」
秋人の背後に覆い被さった歩実が腰から手を回して敏感な部分に触れる。
「ああっ!・・・」
「どうだ感じるか?」
歩実に改めて言われるまでもなく秋人が感じているのは明白だった。人一倍感じる『女』にさせられた彼の脳髄はもう痺れる様な快感を感じ取っていた。
「んふふ、胸までこんなにされて感じているなんて・・・。」
歩実は更に片手を秋人のブラウスの中に強引に潜り込ませ、ブラの上から彼の豊胸された豊満な胸を揉み始める。
「あぁんっ・・・もっと優しく・・・・して・・・。」
手術後間もない為の痛みと、胸でさえも感じる様にされている快感との合間で秋人は思わず本当に初体験の少女の様な声を漏らしてしまった。
「何が『優しくしてだ』、男の癖しやがって!自分の立場分かってるのか!?」
歩実は力まかせに秋人の胸を握った。
「うぎゃーっ!!」
造ったばかりの敏感なところを握り潰される痛みに秋人が悲鳴をあげた。
「言い声出せるじゃないか。そろそろお前の女をもらうからな。」
歩実はそう言ってディルドーの先を秋人の局部に押し当てた。
「やっ・・・やめてっ!やっぱり・・・!」
その熱い肉棒の感触に一瞬我に返った秋人は、娘に犯される、娘に『女』にされるという事実を思い出し、ためらいの声を上げた。しかし歩実の動きが止まることはなかった。
「ほら娘のおちんちんを咥え込みなさい!」
彼女は疑似ペニスを一気に秋人の膣に挿入した。
「あ・・あああ・ああぁ・・ああっ!!」
生まれてから経験したことの無いような甘い快感と屈辱感に秋人は白目を剥きながら喘ぎ声を漏らした。
「んふっ、初めてだからきつきつね。」
ずぼずぼと奥まで挿入される歩実のペニスを体の奥で感じながら、彼はベッドのシーツを両手で握りしめた。
「どうパパ、歩実のおちんちん感じる?」
「ああっ・・・今更・・・そんなこと・・・」
「何が今更なの?実の娘にオマンコ犯されちゃってる癖に。ほらほら!」
「ああっんっ・・ああっ・・・」
腰を動かし始めた歩実のディルドーが膣の内壁を刺激する感覚に、秋人はよだれを垂らしながらも快感に耐えようとしたが体は言う事をきかなかった。
「あははは、もう自分で腰ふってるじゃないの。ほら、おちんちん気持ちいいの?」
「はっ・・・はいっ!・・・あ、歩実様の・・・おちんちんが私のおまんこの奥まで入ってとっても感じちゃっていますっ!あっ・・・もっと・・・もっと!奥まで!・・・」
「初めてなのにこんなに感じちゃって、まったく淫乱なパパね。ほらっ、お望み通りもっと奥まで突いてあげるわ!」
「ひぐぅっ・・・あぁあああぁんっ!!!いっ!・・・いいっっ!!」
実の娘に女子中学生姿でバックから犯されながら、秋人はもう自分が男には戻れないであろうことを心のどこかで覚悟してした。
「じゅるっ・・・」
静かな歩実の部屋に卑猥な音が響き渡り、目を閉じても秋人は自分の行為の破廉恥さを確認させられずにはいられない。
「どう、俺のチンコうまいか?」
歩実が見下ろしながら尋ねる。秋人は上目遣いで従順な彼女を演じるしかなかった。
「う・・・うん・・・とってもおいしいわ・・・。」
細い声で言った秋人の怯える目を見て歩実は加虐心を刺激される。
「じゃあもっと丁寧に濡らすんだ。前みたいに痛い目にあいたくなかったらな。」
秋人はあの夜の事を思い出し恐怖に震える。彼は慌てて唾液を口に含むとディルドーに絡ませる。
「ふふふ、そんなに早く入れて欲しいのか。まだ中学生の癖に淫乱な娘だな。」
そう言いながら趣味は足で秋人の制服のスカートを捲ると、彼の股間に足の指を這わせた。
「あっ・・・だめっ・・・」
女性よりも感じる様にされた秋人は悲鳴の様な喘ぎ声を漏らす。
「ほらっ・・・口が留守だぞ!」
それを知っていて歩実は無理矢理彼の口にディルドーを押し込む。局部の快感に声を上げる事も出来ずに、秋人の恥部は段々と湿っていく。
「なんだ、お前嫌そうにしながらも濡れているじゃないか。」
歩実が秋人の股間から出た愛液で濡れた靴下を彼の顔に押しつける。
「ち・・違う・・・の・・・。」
「何が違うんだ?これはお前が出したものだろう?」
歩実が否定しても、その濡れた靴下から糸を引く液体は彼が感じてしまっている事実を如実に示していた。
「そろそろたまらないんじゃないか?」
歩実の言うとおりだった。口では否定しても体の機能は女にされた秋人にとって、長時間によるフェラチオ奉仕と足責めは彼の『女』を刺激するには十分過ぎた。
「じゃあベッドに四つん這いになれ。」
催眠術でもかけられた様に秋人は娘の指示でベッドに乗る。いけない事とは分かっていても体がそれを拒否出来なかった。
「自分でスカートを捲ってショーツを下ろせ。」
秋人は真っ赤になりながらも歩実の指示に従う。中学生の制服姿でベッドの上で尻を突き出してショーツを自ら下ろす姿はまるで本当に淫乱な小娘の様だった。
「処女のくせにこんなに濡らしやがって。」
秋人の背後に覆い被さった歩実が腰から手を回して敏感な部分に触れる。
「ああっ!・・・」
「どうだ感じるか?」
歩実に改めて言われるまでもなく秋人が感じているのは明白だった。人一倍感じる『女』にさせられた彼の脳髄はもう痺れる様な快感を感じ取っていた。
「んふふ、胸までこんなにされて感じているなんて・・・。」
歩実は更に片手を秋人のブラウスの中に強引に潜り込ませ、ブラの上から彼の豊胸された豊満な胸を揉み始める。
「あぁんっ・・・もっと優しく・・・・して・・・。」
手術後間もない為の痛みと、胸でさえも感じる様にされている快感との合間で秋人は思わず本当に初体験の少女の様な声を漏らしてしまった。
「何が『優しくしてだ』、男の癖しやがって!自分の立場分かってるのか!?」
歩実は力まかせに秋人の胸を握った。
「うぎゃーっ!!」
造ったばかりの敏感なところを握り潰される痛みに秋人が悲鳴をあげた。
「言い声出せるじゃないか。そろそろお前の女をもらうからな。」
歩実はそう言ってディルドーの先を秋人の局部に押し当てた。
「やっ・・・やめてっ!やっぱり・・・!」
その熱い肉棒の感触に一瞬我に返った秋人は、娘に犯される、娘に『女』にされるという事実を思い出し、ためらいの声を上げた。しかし歩実の動きが止まることはなかった。
「ほら娘のおちんちんを咥え込みなさい!」
彼女は疑似ペニスを一気に秋人の膣に挿入した。
「あ・・あああ・ああぁ・・ああっ!!」
生まれてから経験したことの無いような甘い快感と屈辱感に秋人は白目を剥きながら喘ぎ声を漏らした。
「んふっ、初めてだからきつきつね。」
ずぼずぼと奥まで挿入される歩実のペニスを体の奥で感じながら、彼はベッドのシーツを両手で握りしめた。
「どうパパ、歩実のおちんちん感じる?」
「ああっ・・・今更・・・そんなこと・・・」
「何が今更なの?実の娘にオマンコ犯されちゃってる癖に。ほらほら!」
「ああっんっ・・ああっ・・・」
腰を動かし始めた歩実のディルドーが膣の内壁を刺激する感覚に、秋人はよだれを垂らしながらも快感に耐えようとしたが体は言う事をきかなかった。
「あははは、もう自分で腰ふってるじゃないの。ほら、おちんちん気持ちいいの?」
「はっ・・・はいっ!・・・あ、歩実様の・・・おちんちんが私のおまんこの奥まで入ってとっても感じちゃっていますっ!あっ・・・もっと・・・もっと!奥まで!・・・」
「初めてなのにこんなに感じちゃって、まったく淫乱なパパね。ほらっ、お望み通りもっと奥まで突いてあげるわ!」
「ひぐぅっ・・・あぁあああぁんっ!!!いっ!・・・いいっっ!!」
実の娘に女子中学生姿でバックから犯されながら、秋人はもう自分が男には戻れないであろうことを心のどこかで覚悟してした。
娘の妻にされました7
歩実に言われるまま風呂で丹念に体を洗った秋人はリビングに置かれた歩実の制服に袖を通す。洗濯していない為、汗の臭いと共に歩実の香りがして秋人は涙を流す。歩実が中学に入って初めてこの制服を着てみせた時、彼は成長した娘の姿を喜んだものだ。しかしまさか自分がその制服を着る事になるとは思わなかった。
少しだぼだぼのシャツに、自分で穿いてみると歩実が着ている時以上に短く感じるスカート、慣れない手つきで胸のリボンを結び胸に中学のエンブレムの入った上着を着ると、傍目には女子中学生にしか見えない少女が出来上がった。しかし中身は30台の男性なのだ。彼は恥辱に心を染めながら階段を上った。
「おう、ちょっと待ってろ。」
ノックして部屋に入ると歩実は携帯で電話中だった。その携帯も秋人が中学生になった時に買ってやったものである。
「でさぁ、今日うちのたんにんがさぁ・・・。」
「へぇ、うん・・そりゃあきれるよね。あははは」
相手は友人らしい。横から聞いていれば只の女子中学生の会話だ。しかし話はなかなか終わらず10分20分と時が立つ。こんなに恥ずかしい格好を強制されながら、自分などいないかの様に扱われる屈辱にも秋人は文句一つ言う事ができなかった。
「じゃあね。」
ようやく電話が終わり歩実が振り向く。
「待ったか?」
男の様な低い声に戻った彼女は秋人の前に立つと、おもむろにスカートを捲った。
「どうした?ここはもう濡れてるじゃないか・・・。」
歩実の言うとおり秋人の股間は濡れてしまっていた。男というのは悲しいものだ。彼はそんな格好をさせながらも性行為を今から始めるという意識から性的興奮を起こしてしまっていたのだ。ただペニスを失った今の彼はただ局部を濡らすしかそれを表現する方法がなかったのだ。
「じゃあ、まずは舐めてもらおうか。」
歩実はそういうとズボンを脱いでベッドサイドに腰掛けた。腰にはもうディルドーが装着されている、それはいつか秋人のアナル処女を奪った双頭のディルドーだ。
「はい・・・。」
逃げ出すわけにはいかなかった。秋人は歩実の前に跪くとディルドーを両手で握った。
「うぅっ・・・」
疑似ペニスとはいえ、実の娘のものをフェラチオさせられる屈辱に秋人は体が震えた。両手でつかむとそれはとんでもない大きさだった。秋人がかつてつけていたものとは比べものにならない。
「ほら、さっさと咥えろよ。俺の妻なら当然の行為だろうが。」
「は、はいっ・・あなた・・・。」
歩実に急かされ秋人は思いきってその肉棒を口に含んだ。
「ん・・んっ・・・。」
味もなにもしなかったが、これが今まで数多くの歩実の『恋人』を喜ばせてきたという事実を彼は知っていた。彼女達もこうしてフェラチオを強要されたのだろうか?それを考えると秋人は自分が歩実よりも幼い女子中学一年生にされた気分になり益々惨めになる。それを知ってか歩実は更に秋人を辱めた。
「んふふ中学生女子の制服似合ってるわよ、パパ。」
「あ・・・ああっ・・・言わないでっ!」
「なにがよ?いい大人の癖して女子中学生の制服着て娘のおちんちんしゃぶってる変態の癖に!ほら、もっと丁寧に舐めなさい!」
歩実は無理矢理に秋人の口の奥にディルドーを押し込んだ。
「ん・・・ん・・んっ・・・んんっーーーーっ!!」
まるでお口を犯されているかの様な感覚に秋人は気も狂わんほどの恥辱を味わっていた。
少しだぼだぼのシャツに、自分で穿いてみると歩実が着ている時以上に短く感じるスカート、慣れない手つきで胸のリボンを結び胸に中学のエンブレムの入った上着を着ると、傍目には女子中学生にしか見えない少女が出来上がった。しかし中身は30台の男性なのだ。彼は恥辱に心を染めながら階段を上った。
「おう、ちょっと待ってろ。」
ノックして部屋に入ると歩実は携帯で電話中だった。その携帯も秋人が中学生になった時に買ってやったものである。
「でさぁ、今日うちのたんにんがさぁ・・・。」
「へぇ、うん・・そりゃあきれるよね。あははは」
相手は友人らしい。横から聞いていれば只の女子中学生の会話だ。しかし話はなかなか終わらず10分20分と時が立つ。こんなに恥ずかしい格好を強制されながら、自分などいないかの様に扱われる屈辱にも秋人は文句一つ言う事ができなかった。
「じゃあね。」
ようやく電話が終わり歩実が振り向く。
「待ったか?」
男の様な低い声に戻った彼女は秋人の前に立つと、おもむろにスカートを捲った。
「どうした?ここはもう濡れてるじゃないか・・・。」
歩実の言うとおり秋人の股間は濡れてしまっていた。男というのは悲しいものだ。彼はそんな格好をさせながらも性行為を今から始めるという意識から性的興奮を起こしてしまっていたのだ。ただペニスを失った今の彼はただ局部を濡らすしかそれを表現する方法がなかったのだ。
「じゃあ、まずは舐めてもらおうか。」
歩実はそういうとズボンを脱いでベッドサイドに腰掛けた。腰にはもうディルドーが装着されている、それはいつか秋人のアナル処女を奪った双頭のディルドーだ。
「はい・・・。」
逃げ出すわけにはいかなかった。秋人は歩実の前に跪くとディルドーを両手で握った。
「うぅっ・・・」
疑似ペニスとはいえ、実の娘のものをフェラチオさせられる屈辱に秋人は体が震えた。両手でつかむとそれはとんでもない大きさだった。秋人がかつてつけていたものとは比べものにならない。
「ほら、さっさと咥えろよ。俺の妻なら当然の行為だろうが。」
「は、はいっ・・あなた・・・。」
歩実に急かされ秋人は思いきってその肉棒を口に含んだ。
「ん・・んっ・・・。」
味もなにもしなかったが、これが今まで数多くの歩実の『恋人』を喜ばせてきたという事実を彼は知っていた。彼女達もこうしてフェラチオを強要されたのだろうか?それを考えると秋人は自分が歩実よりも幼い女子中学一年生にされた気分になり益々惨めになる。それを知ってか歩実は更に秋人を辱めた。
「んふふ中学生女子の制服似合ってるわよ、パパ。」
「あ・・・ああっ・・・言わないでっ!」
「なにがよ?いい大人の癖して女子中学生の制服着て娘のおちんちんしゃぶってる変態の癖に!ほら、もっと丁寧に舐めなさい!」
歩実は無理矢理に秋人の口の奥にディルドーを押し込んだ。
「ん・・・ん・・んっ・・・んんっーーーーっ!!」
まるでお口を犯されているかの様な感覚に秋人は気も狂わんほどの恥辱を味わっていた。
娘の妻にされました6
「ふふふ、どうだ完全に女になった気分は?」
退院してきた秋人を見て歩実は満足げに言った。可能な限り大きくしてほしいと歩実が注文を付けた胸はEカップはありそうだ。
「あの・・・・胸が・・・苦しくて・・・。」
秋人は慣れない胸を見下ろしながら言った。立ったままの姿勢では自分の下半身さえ見えない。
「これで、もう男物の服は絶対に着れないな。」
歩実はそう言って秋人の胸を軽くなでた。
「やだっ・・・。」
精巧に作られた乳首に痛みとも違和感とも快感とも取れる感覚を感じ、秋人は歩実の手を払いのけた。
「嫌がり方まで女らしくなったじゃないか。しかし、旦那様に逆らうとはどういう事だ?俺はお前をそんな風に躾けた覚えはないぞ?」
当たり前だ。歩実を育てたのは本当は秋人なのだ。しかし、彼は娘に逆らう事は出来ない立場だった。
「ご・・・ごめんなさい・・・・あなた・・・・。」
「いい子だ。じっとしてるんだぞ。」
歩実はそう言うと、秋人の穿いているチェックのミニスカートを捲り上げた。
「いやっ!・・・」
一瞬手が出そうになった秋人だが、すんでのところで手を止める。
「ほら、自分で持っていろ。」
歩実は秋人に、自らの穿いているスカートの裾を捲ったままの状態で持たせると、今度は彼の穿いている薄い水色のショーツに手を掛けた。
「じゃあ、見せてもらおうか。」
歩実は一気にショーツをずり下げた。秋人はまりの恥ずかしさにも、目を閉じることぐらいしか出来ない。
「ふーん。あの医者、言うだけあってよく出来ているぞ。お前ももう見たのか?」
「いえ・・・恥ずかしくって・・・」
秋人は頬を染める。
「少し不格好だが、膣と尿道口はもちろん、ラビアにクリトリスらしいものまで造ってあるぞ。毛が生えていないからまるで子供の様だがな。」
秋人は笑いながら、指でそっと秋人のクリトリスに触れた。
「あんっ!」
思わず口をついて出た喘ぎ声に秋人自身が驚いた。
「どうだ、女性器に触れられた感触は?まるで頭がしびれるようなんじゃないか?」
秋人は素直に頷いた。
「医者の話によると、お前の性器は本物の女性以上に感じる様に造られたそうだ。金はかかったが、さすがの腕だ。」
「ごめんなさい・・・。」
金がかかったと聞いて秋人は謝ったが、その手術料の大半を山中課長が出してくれた事は言わなかった。
「まあいい、これからお前自身が働いて返すんだからな。」
秋人は数日後から、男時代に働いていた会社にOLとして出勤しなくてはいけない事を思い出し、暗鬱な気分に襲われた。
「それから・・・。」
歩実はニヤリと笑って言った。
「今日は俺がお前を女にしてやる。」
多少の覚悟はしていたが、実際に言われるのは衝撃だった。自分は今晩、実の娘に抱かれるのか。そう考えると秋人の頭はおかしくなりそうだった。
「俺の後に風呂に入ったら、これに着替えてベッドで待っていろ。」
それは歩実が通っている中学の女子制服だった。
「処女を失うにはぴったりの衣装だろ。」
もはや歩実の目はぎらぎらとした若い男の様だった。
退院してきた秋人を見て歩実は満足げに言った。可能な限り大きくしてほしいと歩実が注文を付けた胸はEカップはありそうだ。
「あの・・・・胸が・・・苦しくて・・・。」
秋人は慣れない胸を見下ろしながら言った。立ったままの姿勢では自分の下半身さえ見えない。
「これで、もう男物の服は絶対に着れないな。」
歩実はそう言って秋人の胸を軽くなでた。
「やだっ・・・。」
精巧に作られた乳首に痛みとも違和感とも快感とも取れる感覚を感じ、秋人は歩実の手を払いのけた。
「嫌がり方まで女らしくなったじゃないか。しかし、旦那様に逆らうとはどういう事だ?俺はお前をそんな風に躾けた覚えはないぞ?」
当たり前だ。歩実を育てたのは本当は秋人なのだ。しかし、彼は娘に逆らう事は出来ない立場だった。
「ご・・・ごめんなさい・・・・あなた・・・・。」
「いい子だ。じっとしてるんだぞ。」
歩実はそう言うと、秋人の穿いているチェックのミニスカートを捲り上げた。
「いやっ!・・・」
一瞬手が出そうになった秋人だが、すんでのところで手を止める。
「ほら、自分で持っていろ。」
歩実は秋人に、自らの穿いているスカートの裾を捲ったままの状態で持たせると、今度は彼の穿いている薄い水色のショーツに手を掛けた。
「じゃあ、見せてもらおうか。」
歩実は一気にショーツをずり下げた。秋人はまりの恥ずかしさにも、目を閉じることぐらいしか出来ない。
「ふーん。あの医者、言うだけあってよく出来ているぞ。お前ももう見たのか?」
「いえ・・・恥ずかしくって・・・」
秋人は頬を染める。
「少し不格好だが、膣と尿道口はもちろん、ラビアにクリトリスらしいものまで造ってあるぞ。毛が生えていないからまるで子供の様だがな。」
秋人は笑いながら、指でそっと秋人のクリトリスに触れた。
「あんっ!」
思わず口をついて出た喘ぎ声に秋人自身が驚いた。
「どうだ、女性器に触れられた感触は?まるで頭がしびれるようなんじゃないか?」
秋人は素直に頷いた。
「医者の話によると、お前の性器は本物の女性以上に感じる様に造られたそうだ。金はかかったが、さすがの腕だ。」
「ごめんなさい・・・。」
金がかかったと聞いて秋人は謝ったが、その手術料の大半を山中課長が出してくれた事は言わなかった。
「まあいい、これからお前自身が働いて返すんだからな。」
秋人は数日後から、男時代に働いていた会社にOLとして出勤しなくてはいけない事を思い出し、暗鬱な気分に襲われた。
「それから・・・。」
歩実はニヤリと笑って言った。
「今日は俺がお前を女にしてやる。」
多少の覚悟はしていたが、実際に言われるのは衝撃だった。自分は今晩、実の娘に抱かれるのか。そう考えると秋人の頭はおかしくなりそうだった。
「俺の後に風呂に入ったら、これに着替えてベッドで待っていろ。」
それは歩実が通っている中学の女子制服だった。
「処女を失うにはぴったりの衣装だろ。」
もはや歩実の目はぎらぎらとした若い男の様だった。
娘の妻にされました5
「ほ、本当に・・・雪平君かね・・・?」
空いていた会議室に通されて三人きりの部屋の中、歩実から一通りの説明を受けた山中課長は薄くなった頭皮を撫でながら言った。
「はい、僕は付き添いですが、父が退職願を出したいというので付いてきました。」
恥ずかしさに身を縮める秋人を横目でみながら歩実が言った。
「しかし、なんて格好だ・・・。その下着はなんなのかね。それにしても・・・」
彼は秋人の膝に下ろされたままのショーツをいやらしい目で見た。
「それにしても君がこんなに女装が似合うとは思っていなかったよ。」
彼の目は秋人の足に釘付けだ。それを見取った歩実が言う。
「なかなか可愛い女になったでしょう?しかし痴漢などという反社会的犯罪を犯した社員は退職させなければなりませんよね。」
「していない!」という秋人の叫びを歩実は制した。
「うむ・・・通常はそうなんだが・・・。」
「元通り働かせてもらえるのですか!?」
歩実は的を射たりとばかりに言った。課長が秋人に興味がありそうなのは明白だったからだ。実は歩実は秋人を退職させるつもりでここに来たのではなかった。なんとか彼を働かせないと実質の収入が無くなってしまうからだ。
「まぁ、私の一存では決められんが・・・。」
そう言いながらも彼は言い切った。
「それには、手術をして完全に女性になってもらわんとな。」
「えっ!?」
秋人は驚いた。
「その上で君には女子社員として、再度入社してもらおう。もちろん給与は下がるが、どのみちそんな状態では雇ってくれる会社などあるまい。」
いまだに独身の課長がゲイだとかニューハーフ好きだとかいう噂があった事を秋人はようやく思い出した。
「け、結構です!」
そう言った秋人を下がらせて歩実が話す。
「それでしたらこちらとしても望むところです。明日にでも手術を手配して来月あたりから出社させて頂けますか?」
勝手に話を進める歩実に秋人は取り縋った。
「黙れ!女の癖に俺の命令に逆らうつもりか!」
一喝された秋人は泣きながら懇願した。
「お、お願いです・・・女子社員として勤務なんて・・・酷すぎます・・・・恥ずかし過ぎます・・・」
しかし歩実がそれを受け入れるわけは無かった。
数日後秋人は今度は女性器を造る手術を無理矢理に受けさせられ、胸までふくよかに豊胸されてしまったのだ。
空いていた会議室に通されて三人きりの部屋の中、歩実から一通りの説明を受けた山中課長は薄くなった頭皮を撫でながら言った。
「はい、僕は付き添いですが、父が退職願を出したいというので付いてきました。」
恥ずかしさに身を縮める秋人を横目でみながら歩実が言った。
「しかし、なんて格好だ・・・。その下着はなんなのかね。それにしても・・・」
彼は秋人の膝に下ろされたままのショーツをいやらしい目で見た。
「それにしても君がこんなに女装が似合うとは思っていなかったよ。」
彼の目は秋人の足に釘付けだ。それを見取った歩実が言う。
「なかなか可愛い女になったでしょう?しかし痴漢などという反社会的犯罪を犯した社員は退職させなければなりませんよね。」
「していない!」という秋人の叫びを歩実は制した。
「うむ・・・通常はそうなんだが・・・。」
「元通り働かせてもらえるのですか!?」
歩実は的を射たりとばかりに言った。課長が秋人に興味がありそうなのは明白だったからだ。実は歩実は秋人を退職させるつもりでここに来たのではなかった。なんとか彼を働かせないと実質の収入が無くなってしまうからだ。
「まぁ、私の一存では決められんが・・・。」
そう言いながらも彼は言い切った。
「それには、手術をして完全に女性になってもらわんとな。」
「えっ!?」
秋人は驚いた。
「その上で君には女子社員として、再度入社してもらおう。もちろん給与は下がるが、どのみちそんな状態では雇ってくれる会社などあるまい。」
いまだに独身の課長がゲイだとかニューハーフ好きだとかいう噂があった事を秋人はようやく思い出した。
「け、結構です!」
そう言った秋人を下がらせて歩実が話す。
「それでしたらこちらとしても望むところです。明日にでも手術を手配して来月あたりから出社させて頂けますか?」
勝手に話を進める歩実に秋人は取り縋った。
「黙れ!女の癖に俺の命令に逆らうつもりか!」
一喝された秋人は泣きながら懇願した。
「お、お願いです・・・女子社員として勤務なんて・・・酷すぎます・・・・恥ずかし過ぎます・・・」
しかし歩実がそれを受け入れるわけは無かった。
数日後秋人は今度は女性器を造る手術を無理矢理に受けさせられ、胸までふくよかに豊胸されてしまったのだ。
娘の妻にされました4
「いつまで女みたいにメソメソ泣いているんだ!」
スカートの裾を押さえて、とうとう泣き出してしまった秋人を歩実が叱り付ける。
「はい、あなた・・・」
これ以上怒らせると歩実が何をするか分からないのはこれまでの経験で知っていた。秋人は目の涙を拭って立ち上がる。
「きちんと課長さんに挨拶するんだぞ。さんざんお世話になったんだからな。」
乗り慣れたエレベーターで娘に説教を受けるとは、ほんの一ヶ月前には夢にも思わなかった。秋人はめまいさえ感じる程の恥辱の中、営業部のある三階に下りた。
若い男性とキャミワンピ姿の女性という部内にありえない二人に廊下に立っていた社員は唖然とする。そのうち気を利かせた一人の女子社員が二人に近寄ってきた。
「どちらに御用ですか?」
「ほら、自分で用件をいいなさい!」
歩実が秋人の肩を叩いた。
「あ、あの・・・。」
女子社員は秋人の元部下だった。彼はくちごもりながらようやく言った。
「あの・・・や、山中課長様に・・・。」
言った途端女性の顔が曇る。声で正体が知れたのかも知れなかった。
「ひょ・・・ひょっとして・・・・。」
「はい、雪平です。」
歩実がこともなげに答えた。
「ほら、知り合いの方ならきちんと挨拶しなさい。」
「で、でも・・・」
もう秋人はパニック状態だった。それもそうだろう一ヶ月前まで部下だった女の子の前で、あられもない女装姿で立っているのだ。
「こいつが女として生まれ変わりたいと言うんでね。今日は退職の挨拶に来たんですよ・・・ほら、お世話になったお礼とお詫びを申し上げろ!」
「お、お詫び・・・ですか?」
「そうだ。『今まで男の振りして偉そうにしていて申し訳ありません。私は女になりますので、女性の先輩として私にいろいろと教育をお願いします。』ってな。」
「そ・・そんな・・・。」
二人のやりとりを見ていた女性社員は突然高らかに笑った。
「あはははっ。係長にそんな趣味があったなんて全くしらなかったわ。おまけにもう格好いい彼氏さんまで連れちゃって・・・隅におけないわね。もう処女は奪ってもらった?」
まさか歩実が娘だと思わない女子社員の卑猥な言葉に秋人は頬を染める。
「ふん、今までよくも偉そうに上司面をしてくれたわね。ほら、彼氏さんの言うとおり丁寧に謝りなさいよ!」
こうなっては秋人に逃げ場は無い。彼は死ぬ思いで口にした。
「あ・・・あの・・・今まで・・・偉そうにしてしまって・・・も、申し訳ありませんでした・・・。こ・・・これから・・・わ、私は・・・・お、女に・・・なりますので・・・よろしく・・・ご指導・・・下さいませ・・・。」
「ふーん、殊勝じゃないの。じゃあ早速教育してあげるわ!」
女性社員は秋人のスカートに腕を入れると、レースのついた白いショーツをずり下げた。
「うわっ!何もないじゃん!」
男性器も女性器も無い股間を見て、さすがに彼女は驚いた。
「そうなんですよ。さっさと女にしてもらえって僕は言ってるんですけどね・・・よし、このままの格好で課長に会いにいくか。」
あまりの事に放心状態で悲鳴さえ上げられなかった秋人は、膝にショーツを絡ませたノーパン姿の状態で秋人に営業部の廊下を行進させられる。先程のやりとりを見ていた男性社員から卑猥な声が漏れる。
「係長、丸出しのお尻可愛いよ!そんなに犯してほしいなら便所で犯ってやろうか!?」
まだ二十歳そこそこの部下の言葉にも秋人は黙って顔を染めるしかなかった。
スカートの裾を押さえて、とうとう泣き出してしまった秋人を歩実が叱り付ける。
「はい、あなた・・・」
これ以上怒らせると歩実が何をするか分からないのはこれまでの経験で知っていた。秋人は目の涙を拭って立ち上がる。
「きちんと課長さんに挨拶するんだぞ。さんざんお世話になったんだからな。」
乗り慣れたエレベーターで娘に説教を受けるとは、ほんの一ヶ月前には夢にも思わなかった。秋人はめまいさえ感じる程の恥辱の中、営業部のある三階に下りた。
若い男性とキャミワンピ姿の女性という部内にありえない二人に廊下に立っていた社員は唖然とする。そのうち気を利かせた一人の女子社員が二人に近寄ってきた。
「どちらに御用ですか?」
「ほら、自分で用件をいいなさい!」
歩実が秋人の肩を叩いた。
「あ、あの・・・。」
女子社員は秋人の元部下だった。彼はくちごもりながらようやく言った。
「あの・・・や、山中課長様に・・・。」
言った途端女性の顔が曇る。声で正体が知れたのかも知れなかった。
「ひょ・・・ひょっとして・・・・。」
「はい、雪平です。」
歩実がこともなげに答えた。
「ほら、知り合いの方ならきちんと挨拶しなさい。」
「で、でも・・・」
もう秋人はパニック状態だった。それもそうだろう一ヶ月前まで部下だった女の子の前で、あられもない女装姿で立っているのだ。
「こいつが女として生まれ変わりたいと言うんでね。今日は退職の挨拶に来たんですよ・・・ほら、お世話になったお礼とお詫びを申し上げろ!」
「お、お詫び・・・ですか?」
「そうだ。『今まで男の振りして偉そうにしていて申し訳ありません。私は女になりますので、女性の先輩として私にいろいろと教育をお願いします。』ってな。」
「そ・・そんな・・・。」
二人のやりとりを見ていた女性社員は突然高らかに笑った。
「あはははっ。係長にそんな趣味があったなんて全くしらなかったわ。おまけにもう格好いい彼氏さんまで連れちゃって・・・隅におけないわね。もう処女は奪ってもらった?」
まさか歩実が娘だと思わない女子社員の卑猥な言葉に秋人は頬を染める。
「ふん、今までよくも偉そうに上司面をしてくれたわね。ほら、彼氏さんの言うとおり丁寧に謝りなさいよ!」
こうなっては秋人に逃げ場は無い。彼は死ぬ思いで口にした。
「あ・・・あの・・・今まで・・・偉そうにしてしまって・・・も、申し訳ありませんでした・・・。こ・・・これから・・・わ、私は・・・・お、女に・・・なりますので・・・よろしく・・・ご指導・・・下さいませ・・・。」
「ふーん、殊勝じゃないの。じゃあ早速教育してあげるわ!」
女性社員は秋人のスカートに腕を入れると、レースのついた白いショーツをずり下げた。
「うわっ!何もないじゃん!」
男性器も女性器も無い股間を見て、さすがに彼女は驚いた。
「そうなんですよ。さっさと女にしてもらえって僕は言ってるんですけどね・・・よし、このままの格好で課長に会いにいくか。」
あまりの事に放心状態で悲鳴さえ上げられなかった秋人は、膝にショーツを絡ませたノーパン姿の状態で秋人に営業部の廊下を行進させられる。先程のやりとりを見ていた男性社員から卑猥な声が漏れる。
「係長、丸出しのお尻可愛いよ!そんなに犯してほしいなら便所で犯ってやろうか!?」
まだ二十歳そこそこの部下の言葉にも秋人は黙って顔を染めるしかなかった。
娘の妻にされました3
白いシャツに男物のジーンズという姿の歩実に腕を引かれ、秋人は春の暖かい日差しの中で気も狂わんばかりの恥ずかしさを味わっていた。
今までも何回か女装姿で買い物に行かされた事はあるが、スカート姿での外出は初めてだった。しかも家できさされている大人しめのスカートとは違って、すれ違う男性が皆凝視するほど短い丈のキャミワンピである。
「ほら、あまり恥ずかしがると化粧が崩れるぞ。」
歩実にそう言われても、顔から出る汗は止まらなかった。
二人はそのままの姿で地下鉄に乗り込む。それは秋人がほんの少し前まで通勤に使っていた路線だ。端から見れば若い男女のカップルにしか見えないかもしれないが、実際のところは女装した父親と男装した娘なのだ。乗り慣れた車両に娘に手を引かれて乗り込んだ秋人は人々の好奇の目に晒されながら吊革を握りしめた。
「あ、あなた・・・お、お許し下さい!」
歩実に逆らってはいけないことを知りつつ秋人はさすがに大きな声で懇願した。
「どうしてだ?お前はここに用があるんじゃないのか?」
「そ、それは・・・・でも・・・」
駅を降りた時から嫌な予感はあった。しかし、いくらなんでもここに連れて来られるとは思わなかった。そう、この間まで秋人が勤めていた会社に。
「ほら、俺も付いていってやるからさっさと来い!」
歩実は乱暴に秋人の手を握ると嫌がる彼を引きずる様に社内に連れ込んだ。
「いらっしゃいませ。どういったご用件でしょうか?」
可愛らしいピンクの制服を着た受付嬢が、その場にふさわしくない服装の二人に尋ねる。
「雪平ですけど、営業部の山中課長に用がありまして。」
歩実が答える。受付嬢と知り合いの秋人は顔を上げることもできない。
「どういったご用件でしょうか?」
「こいつの退職手続きを行いに来ました。ほら、挨拶しろ!」
秋人は下を向いていた秋人の顔を無理矢理上げさせる。秋人の顔と「雪平」という珍しい名字で彼の正体に気が付いた受付嬢は唖然とした表情をした。
「ゆ、雪平さん・・・なんて格好を・・・。」
秋人はあまりの恥ずかしさに言い訳さえ思いつかなかった。
「こいつはね、女装趣味が高じて女になりたいみたいなんだ。あっ、遅れました私は息子のあゆむです。」
受付嬢は歩実の言葉を鵜呑みにし、クスクスと笑いながら答えた。
「まぁ、そうだったんですか。でもとってもお似合いですよ。私前から雪平さん女性っぽいなと思ってたんです。」
「そうでしょ、まぁ僕もオヤジがこんなになって驚いてるけどね。」
歩実はこともなげに答えた。
「でしたら、営業部は三階ですのでどうぞ。」
受付嬢はロビーのエレベーターを指し示した。
「どうも、ありがとう。ほら、いくぞ秋人!」
二人の恋人の様なやりとりを見て受付嬢は笑いを堪えきれずに言った。
「雪平さん、とってもお似合いのカップルですけど・・・服装はお年のわりに派手すぎですよ!」
「ほら、言った通りだろ。いい年して若い娘みたいな服が着たいなんていいやがって。ほら、パンツ見えそうじゃないか。」
歩実はそう言いながら、秋人のキャミワンピの裾をつまんだ。
「きゃっ!」
秋人は慌てて裾を押さえる。
「まぁ!下着まで女物なんですね!」
受付嬢が驚く。後輩の若い女性にパンチラを見られたショックに秋人はロビーの柔らかな絨毯に足から崩れ落ちた。
今までも何回か女装姿で買い物に行かされた事はあるが、スカート姿での外出は初めてだった。しかも家できさされている大人しめのスカートとは違って、すれ違う男性が皆凝視するほど短い丈のキャミワンピである。
「ほら、あまり恥ずかしがると化粧が崩れるぞ。」
歩実にそう言われても、顔から出る汗は止まらなかった。
二人はそのままの姿で地下鉄に乗り込む。それは秋人がほんの少し前まで通勤に使っていた路線だ。端から見れば若い男女のカップルにしか見えないかもしれないが、実際のところは女装した父親と男装した娘なのだ。乗り慣れた車両に娘に手を引かれて乗り込んだ秋人は人々の好奇の目に晒されながら吊革を握りしめた。
「あ、あなた・・・お、お許し下さい!」
歩実に逆らってはいけないことを知りつつ秋人はさすがに大きな声で懇願した。
「どうしてだ?お前はここに用があるんじゃないのか?」
「そ、それは・・・・でも・・・」
駅を降りた時から嫌な予感はあった。しかし、いくらなんでもここに連れて来られるとは思わなかった。そう、この間まで秋人が勤めていた会社に。
「ほら、俺も付いていってやるからさっさと来い!」
歩実は乱暴に秋人の手を握ると嫌がる彼を引きずる様に社内に連れ込んだ。
「いらっしゃいませ。どういったご用件でしょうか?」
可愛らしいピンクの制服を着た受付嬢が、その場にふさわしくない服装の二人に尋ねる。
「雪平ですけど、営業部の山中課長に用がありまして。」
歩実が答える。受付嬢と知り合いの秋人は顔を上げることもできない。
「どういったご用件でしょうか?」
「こいつの退職手続きを行いに来ました。ほら、挨拶しろ!」
秋人は下を向いていた秋人の顔を無理矢理上げさせる。秋人の顔と「雪平」という珍しい名字で彼の正体に気が付いた受付嬢は唖然とした表情をした。
「ゆ、雪平さん・・・なんて格好を・・・。」
秋人はあまりの恥ずかしさに言い訳さえ思いつかなかった。
「こいつはね、女装趣味が高じて女になりたいみたいなんだ。あっ、遅れました私は息子のあゆむです。」
受付嬢は歩実の言葉を鵜呑みにし、クスクスと笑いながら答えた。
「まぁ、そうだったんですか。でもとってもお似合いですよ。私前から雪平さん女性っぽいなと思ってたんです。」
「そうでしょ、まぁ僕もオヤジがこんなになって驚いてるけどね。」
歩実はこともなげに答えた。
「でしたら、営業部は三階ですのでどうぞ。」
受付嬢はロビーのエレベーターを指し示した。
「どうも、ありがとう。ほら、いくぞ秋人!」
二人の恋人の様なやりとりを見て受付嬢は笑いを堪えきれずに言った。
「雪平さん、とってもお似合いのカップルですけど・・・服装はお年のわりに派手すぎですよ!」
「ほら、言った通りだろ。いい年して若い娘みたいな服が着たいなんていいやがって。ほら、パンツ見えそうじゃないか。」
歩実はそう言いながら、秋人のキャミワンピの裾をつまんだ。
「きゃっ!」
秋人は慌てて裾を押さえる。
「まぁ!下着まで女物なんですね!」
受付嬢が驚く。後輩の若い女性にパンチラを見られたショックに秋人はロビーの柔らかな絨毯に足から崩れ落ちた。
娘の妻にされました2
「なんだよ、今日も簡単な丼モノか。そんな事で俺の妻が務まると思ってるのか!」
男物の私服に着替えて食卓に着くなり、歩実は秋人を怒鳴りつけた。
「ご、ごめんなさい・・・あなた・・・まだ慣れ無くって・・・。」
「まったく、女の癖に全然料理ができないんだからな。」
それは以前歩実が秋人によく言われた言葉だった。
「それよりどうだ、ここの具合は・・・」
歩実はそう言って傍らに立ってお茶を注いでいる秋人の股間に触れた。
「ま、まだ・・・変な気分です・・・・。」
秋人は恥ずかしげに答える。彼のその部分には一ヶ月前までの膨らみは無かった。あの日、なんとか自分で車を運転して駆け込んだ病院で、医者から告げられたのは残酷な言葉だった。
「残念ですが手遅れです。切除するしかありません。」
その日の内に秋人は男性器を失った。
「それで覚悟はできたのか?・・・女になる。」
今の彼はいわば男性器を失っただけの性的不能名だけの状態だった。歩実は男性器のあった部分に女性器を作るように進言していたのだ。
「ま、まだそこまでは・・・。」
秋人は小さな声で答えた。ついこの間まで立派な男性だった彼が即答できる筈も無かった。
「なんだ、まだ自分の立場が分かってないらしいな。」
歩実はまるで男性の様に丼を左手で持ち上げ、右手に持った箸で掻き込みながら言った。
「もうお前は男には戻れないんだ。折角俺が嫁にもらってやると言っているのに、いい加減決断したらどうだ。」
秋人は正面に座って俯いているままだった。食事も喉を通る筈がなかった。
「よし、じゃあ俺がふんぎりをつけさせてやる。明日は二人で出かけるぞ。」
「えっ、でも・・・あゆむさん学校は・・・」
「そんなもん休めばいい。デートしてやると言っているのに不満か?」
秋人は青くなって言った。
「いいえ、滅相もございません。」
翌日。
「あ、あなた・・・本当にこんな格好で外に出るんですの?」
秋人が歩実に指定されて着せられたのは妻の若い頃の服、股下何センチかというスケスケの生地でできたキャミワンピだった。
「なんだ、不満なのか?似合ってるから心配するな。」
確かに色の白い秋人には、そのうっすらとしたピンク色のキャミワンピは似合っていた。全身の毛は毎日丁寧に剃らされているため体毛も見苦しくない。
しかしいくら華奢で女顔だといっても秋人はもう三十代なかばの男性だ。その十代の女の子向けの洋服を着て違和感が無い訳はなかった。
「こんな格好で・・・一体・・・・」
歩実に無理矢理外に連れ出された秋人は、まるで何も穿いていないかの様な下半身の頼りなさに恐怖さえ感じていた。
男物の私服に着替えて食卓に着くなり、歩実は秋人を怒鳴りつけた。
「ご、ごめんなさい・・・あなた・・・まだ慣れ無くって・・・。」
「まったく、女の癖に全然料理ができないんだからな。」
それは以前歩実が秋人によく言われた言葉だった。
「それよりどうだ、ここの具合は・・・」
歩実はそう言って傍らに立ってお茶を注いでいる秋人の股間に触れた。
「ま、まだ・・・変な気分です・・・・。」
秋人は恥ずかしげに答える。彼のその部分には一ヶ月前までの膨らみは無かった。あの日、なんとか自分で車を運転して駆け込んだ病院で、医者から告げられたのは残酷な言葉だった。
「残念ですが手遅れです。切除するしかありません。」
その日の内に秋人は男性器を失った。
「それで覚悟はできたのか?・・・女になる。」
今の彼はいわば男性器を失っただけの性的不能名だけの状態だった。歩実は男性器のあった部分に女性器を作るように進言していたのだ。
「ま、まだそこまでは・・・。」
秋人は小さな声で答えた。ついこの間まで立派な男性だった彼が即答できる筈も無かった。
「なんだ、まだ自分の立場が分かってないらしいな。」
歩実はまるで男性の様に丼を左手で持ち上げ、右手に持った箸で掻き込みながら言った。
「もうお前は男には戻れないんだ。折角俺が嫁にもらってやると言っているのに、いい加減決断したらどうだ。」
秋人は正面に座って俯いているままだった。食事も喉を通る筈がなかった。
「よし、じゃあ俺がふんぎりをつけさせてやる。明日は二人で出かけるぞ。」
「えっ、でも・・・あゆむさん学校は・・・」
「そんなもん休めばいい。デートしてやると言っているのに不満か?」
秋人は青くなって言った。
「いいえ、滅相もございません。」
翌日。
「あ、あなた・・・本当にこんな格好で外に出るんですの?」
秋人が歩実に指定されて着せられたのは妻の若い頃の服、股下何センチかというスケスケの生地でできたキャミワンピだった。
「なんだ、不満なのか?似合ってるから心配するな。」
確かに色の白い秋人には、そのうっすらとしたピンク色のキャミワンピは似合っていた。全身の毛は毎日丁寧に剃らされているため体毛も見苦しくない。
しかしいくら華奢で女顔だといっても秋人はもう三十代なかばの男性だ。その十代の女の子向けの洋服を着て違和感が無い訳はなかった。
「こんな格好で・・・一体・・・・」
歩実に無理矢理外に連れ出された秋人は、まるで何も穿いていないかの様な下半身の頼りなさに恐怖さえ感じていた。
娘の妻にされました1
「あ、歩実さん、お帰りなさいませ。」
雪平秋人は水色のワンピースにフリフリのエプロン姿で、学校から帰ってきたばかりの実の娘、雪平歩実に頭を下げた。
「家では『あゆむ』だって言っただろうが!」
グレーのジャケットにチェックのスカートという女子中学生姿のままで、歩実は父親である秋人の頬を平手打ちした。
「きゃっ!」
秋人は両手で自らの頬を押さえる。
「ふん、悲鳴だけは女じゃないか。ほら腹減ったから、これ片付けたらさっさと夕食の支度をしろ!」
歩実は乱暴に言って、部活用の大きなスポーツバッグを秋人に投げつけた。
「は、はいっ・・・あ、あゆむさん。」
秋人はそう言ってバッグを抱えて洗濯機に向かった。
秋人と歩実の関係がこの様になったのはほんの一ヶ月前。秋人が出勤時に痴漢で捕まるという事件のせいだった。必死に犯行を否定した秋人だったが、日頃から家族に信用の無い彼は妻と息子に実家に帰られてしまい、残ったのは中学2年生になる娘の歩実だけだった。
歩実とて好んで家に残った訳でなく、居心地の良い学校生活を壊したくないだけだった。母親の実家からではとても通える距離ではない学校の友人達を彼女は失いたくはなかったのだ。
秋人は歩実が残ってくれる事を『自分を信用してくれた』と勘違いして大層喜んだが、歩実の提案した『パパと一緒に暮らす条件』は苛烈なものだった。
一つには秋人は女性として振る舞う事。これは、痴漢などという破廉恥な罪を犯した(かもしれない)男性と一つ屋根の下で暮らすのは落ち着かない。せめて女性の格好をしていれば安心できるという歩実の言い分だった。秋人は初め、娘の前で女装なんて耐えられないと思ったが、痴漢の疑いをかけられたまま一人で暮らすのは更に耐え難い苦痛だと感じ、娘の提案を受け入れた。
しかし一週間後、今度歩実の方が男性として家で過ごし始めたのだ。
「ど、どうしたんだい。男物の下着なんか穿いて。」
風呂上がり、トランクス一枚の姿でリビングにやってきた歩実を見て秋人は驚いた。小学校低学年の頃以来見ていない胸はすっかりと大きくなっており、実の娘の裸体に彼は一瞬ドキリとした。
「わたしさぁ、実は男の子になりたいと思ってたんだ。」
洗い物をしている秋人の傍まで近寄ると、歩実は照れくさそうに言った。
「そ、そうなのか・・・」
言われた通り、暮らし始めてから着さされている妻のお古のスカート姿の秋人は、自分より背の高い娘の初めての告白に驚きを隠せなかった。
「だって、パパも弟もなんだか自由な感じだし・・・・」
歩実は秋人のお尻に手を伸ばした。
「こういうのって男の特権だよね。」
「な、何をするんだ!」
娘にお尻を撫でられて、秋人は慌てて飛び退いた。
「んふふ、やっぱり面白いわぁ・・・・パパったら可愛いから、我慢できなくなっちゃった。」
「な、何を?!」
歩実の倒錯した発言はあながち嘘ではなかった。母親に似て大柄で中学2年ながら170センチはあり、肩幅も広い歩実と、160センチ程度しかない小柄で華奢な父親の秋人。おまけに女装までしているものだから今の秋人は若い女性にしか見えなかった。
「何を?って言った通りよ。さぁ、可愛がってあげるわ。こっちきなさい。」
歩実は乱暴に秋人の手をつかむと無理矢理押し倒した。
「やっ!」
「んふふ、女の子みたいに鳴いちゃって。」
歩実は倒れたままの秋人の両手を片手で押さえ付けると、もう片方の手を彼のスカートに潜り込ませた。
「や、やめっ!」
いつのまにこんなに大きくなったのか、押さえられている腕はビクリともしない。
「どう?娘に犯される気分は・・・優しくしてあげるから大人しくしてなさいね。」
歩実はスカートの中の指を秋人の陰部に這わせる。妻のお古のショーツのレースが微かな音を立てた。
「んふふ、嫌がりながらも勃ってきたじゃない。」
歩実の言うとおり、秋人のものはこんな状態でも勃起を始めていた。
「女の子扱いされるのも満更じゃないでしょ?」
いけないとは思いながらも秋人は抵抗できないままスカートの前部分を大きくしていった。
「じゃまねぇ、脱がしちゃお。」
しばらくしてまだるっこしくなった歩実は秋人のスカートを脱がそうとするが、ペニスが邪魔で脱がすことができない。
「もー!」
憤った歩実は脇のファスナーの部分を力強く引っ張った。『ビリッ!』という音がし、スカートが大きく引き裂かれて秋人のレースのショーツが露わになる。
「や・・・やめて・・・。」
まるでレイプされているかの様な状態で秋人は腰を抜かして立つことができなかった。
「力抜きなさいね。」
歩実は身動き出来ない秋人の身体を半回転させ四つん這いにさせると、彼女がいつも後輩を可愛がる時に使っている双頭のディルドーを自らの股間に突き刺した。
「や、やめてっ!お願いっ!!」
秋人の叫びは歩実を興奮させるだけだった。
「ほら、処女もらうわよ。」
「あああーーっつぅっぅううう・・・・・」
ゆっくりと秋人のアナルにディルドーが挿入されていく。
「あー、なんだか、女の子犯してるより興奮するわ。」
「ひーっ!いたいっ!いたいっ!!」
恍惚状態の歩実は秋人の悲鳴などおかまいなしに腰を動かし続けた。
「なぁ、お前俺の嫁になれよ。たっぷりと可愛がってやるから。」
もはやイってしまった目で歩実が囁く。
「ひーっ!ひっっっ!!」
秋人はあまりの痛さに声も出ない。歩実はその髪の毛をつかんで頭を引っ張り上げた。
「おら、返事はどうした?言わないと一生抜いてやらないぞ!」
「ひっ!!い、いいます!いいますからっ!!」
秋人は激痛から逃れる事しか頭になかった。
「じゃあ言って見ろ。『歩実さんの妻にして下さいませ』ってな。」
「は、はい・・・わ、わたしを・・・あ、歩実さんの妻にして下さいませっ!」
「ふふふ、いい子だ。じゃあこっちはもういらないわね。」
馬乗り状態の歩実は完全に勃起した秋人の陰部を力まかせに握りしめた。
「うぎゃーっっ!!」
秋人の射精と同時に『ぐじゃっ』という嫌な音がリビングに響いた・・・。
雪平秋人は水色のワンピースにフリフリのエプロン姿で、学校から帰ってきたばかりの実の娘、雪平歩実に頭を下げた。
「家では『あゆむ』だって言っただろうが!」
グレーのジャケットにチェックのスカートという女子中学生姿のままで、歩実は父親である秋人の頬を平手打ちした。
「きゃっ!」
秋人は両手で自らの頬を押さえる。
「ふん、悲鳴だけは女じゃないか。ほら腹減ったから、これ片付けたらさっさと夕食の支度をしろ!」
歩実は乱暴に言って、部活用の大きなスポーツバッグを秋人に投げつけた。
「は、はいっ・・・あ、あゆむさん。」
秋人はそう言ってバッグを抱えて洗濯機に向かった。
秋人と歩実の関係がこの様になったのはほんの一ヶ月前。秋人が出勤時に痴漢で捕まるという事件のせいだった。必死に犯行を否定した秋人だったが、日頃から家族に信用の無い彼は妻と息子に実家に帰られてしまい、残ったのは中学2年生になる娘の歩実だけだった。
歩実とて好んで家に残った訳でなく、居心地の良い学校生活を壊したくないだけだった。母親の実家からではとても通える距離ではない学校の友人達を彼女は失いたくはなかったのだ。
秋人は歩実が残ってくれる事を『自分を信用してくれた』と勘違いして大層喜んだが、歩実の提案した『パパと一緒に暮らす条件』は苛烈なものだった。
一つには秋人は女性として振る舞う事。これは、痴漢などという破廉恥な罪を犯した(かもしれない)男性と一つ屋根の下で暮らすのは落ち着かない。せめて女性の格好をしていれば安心できるという歩実の言い分だった。秋人は初め、娘の前で女装なんて耐えられないと思ったが、痴漢の疑いをかけられたまま一人で暮らすのは更に耐え難い苦痛だと感じ、娘の提案を受け入れた。
しかし一週間後、今度歩実の方が男性として家で過ごし始めたのだ。
「ど、どうしたんだい。男物の下着なんか穿いて。」
風呂上がり、トランクス一枚の姿でリビングにやってきた歩実を見て秋人は驚いた。小学校低学年の頃以来見ていない胸はすっかりと大きくなっており、実の娘の裸体に彼は一瞬ドキリとした。
「わたしさぁ、実は男の子になりたいと思ってたんだ。」
洗い物をしている秋人の傍まで近寄ると、歩実は照れくさそうに言った。
「そ、そうなのか・・・」
言われた通り、暮らし始めてから着さされている妻のお古のスカート姿の秋人は、自分より背の高い娘の初めての告白に驚きを隠せなかった。
「だって、パパも弟もなんだか自由な感じだし・・・・」
歩実は秋人のお尻に手を伸ばした。
「こういうのって男の特権だよね。」
「な、何をするんだ!」
娘にお尻を撫でられて、秋人は慌てて飛び退いた。
「んふふ、やっぱり面白いわぁ・・・・パパったら可愛いから、我慢できなくなっちゃった。」
「な、何を?!」
歩実の倒錯した発言はあながち嘘ではなかった。母親に似て大柄で中学2年ながら170センチはあり、肩幅も広い歩実と、160センチ程度しかない小柄で華奢な父親の秋人。おまけに女装までしているものだから今の秋人は若い女性にしか見えなかった。
「何を?って言った通りよ。さぁ、可愛がってあげるわ。こっちきなさい。」
歩実は乱暴に秋人の手をつかむと無理矢理押し倒した。
「やっ!」
「んふふ、女の子みたいに鳴いちゃって。」
歩実は倒れたままの秋人の両手を片手で押さえ付けると、もう片方の手を彼のスカートに潜り込ませた。
「や、やめっ!」
いつのまにこんなに大きくなったのか、押さえられている腕はビクリともしない。
「どう?娘に犯される気分は・・・優しくしてあげるから大人しくしてなさいね。」
歩実はスカートの中の指を秋人の陰部に這わせる。妻のお古のショーツのレースが微かな音を立てた。
「んふふ、嫌がりながらも勃ってきたじゃない。」
歩実の言うとおり、秋人のものはこんな状態でも勃起を始めていた。
「女の子扱いされるのも満更じゃないでしょ?」
いけないとは思いながらも秋人は抵抗できないままスカートの前部分を大きくしていった。
「じゃまねぇ、脱がしちゃお。」
しばらくしてまだるっこしくなった歩実は秋人のスカートを脱がそうとするが、ペニスが邪魔で脱がすことができない。
「もー!」
憤った歩実は脇のファスナーの部分を力強く引っ張った。『ビリッ!』という音がし、スカートが大きく引き裂かれて秋人のレースのショーツが露わになる。
「や・・・やめて・・・。」
まるでレイプされているかの様な状態で秋人は腰を抜かして立つことができなかった。
「力抜きなさいね。」
歩実は身動き出来ない秋人の身体を半回転させ四つん這いにさせると、彼女がいつも後輩を可愛がる時に使っている双頭のディルドーを自らの股間に突き刺した。
「や、やめてっ!お願いっ!!」
秋人の叫びは歩実を興奮させるだけだった。
「ほら、処女もらうわよ。」
「あああーーっつぅっぅううう・・・・・」
ゆっくりと秋人のアナルにディルドーが挿入されていく。
「あー、なんだか、女の子犯してるより興奮するわ。」
「ひーっ!いたいっ!いたいっ!!」
恍惚状態の歩実は秋人の悲鳴などおかまいなしに腰を動かし続けた。
「なぁ、お前俺の嫁になれよ。たっぷりと可愛がってやるから。」
もはやイってしまった目で歩実が囁く。
「ひーっ!ひっっっ!!」
秋人はあまりの痛さに声も出ない。歩実はその髪の毛をつかんで頭を引っ張り上げた。
「おら、返事はどうした?言わないと一生抜いてやらないぞ!」
「ひっ!!い、いいます!いいますからっ!!」
秋人は激痛から逃れる事しか頭になかった。
「じゃあ言って見ろ。『歩実さんの妻にして下さいませ』ってな。」
「は、はい・・・わ、わたしを・・・あ、歩実さんの妻にして下さいませっ!」
「ふふふ、いい子だ。じゃあこっちはもういらないわね。」
馬乗り状態の歩実は完全に勃起した秋人の陰部を力まかせに握りしめた。
「うぎゃーっっ!!」
秋人の射精と同時に『ぐじゃっ』という嫌な音がリビングに響いた・・・。
痴漢で目覚めた僕終了
きまぐれで始めたBLOGですが、昨日からえらく沢山の方に来て頂いて戦々恐々しており、思わず中途半端にお話を終わらしてしまいました。
何も考えずに書き始めたので、女装小説としても性転換小説としても中途半端になってしまいました。ごめんなさい。次回作がんばります。
というわけで、娘の妻にされるお父さんのお話、早速始まります。
何も考えずに書き始めたので、女装小説としても性転換小説としても中途半端になってしまいました。ごめんなさい。次回作がんばります。
というわけで、娘の妻にされるお父さんのお話、早速始まります。
痴漢で目覚めた僕10
気が付いたら悠真は病院のベッドに寝かされていた。
「大丈夫?」
見ればベッドの傍には菜穂子に先程のOLに女子大生に女子高生。先程までかれを陵辱していた面々が顔を揃えていた。
「ひっ!」
一瞬の間に何が起こったのかを思い出し、悠真は悲鳴を上げた。
「心配しなくていいわよ、ここは私の知り合いの病院だから。」
菜穂子が笑う。
「あっ、あの・・・僕の・・・怪我は・・・・。」
加害者が目の前にいるため「怪我」という表現を使って悠真は尋ねた。
「大丈夫よ。なんともないわ。」
菜穂子の返事に悠真は安堵した。
「じゃ、じゃあもう家に帰ります。」
起き上がろうとした悠真を4人が押さえ込む。その時悠真は初めてピンクのハート柄の女性用のパジャマを着せられていることに気が付いた。
「な、何をするんですか!何も無いなら帰らせて下さい!」
悠真の叫びに4人は顔を見合わせた。
「もちろん、なんともないわよ。女の子としてはね。」
菜穂子の言葉の意味がわからず悠真は首を捻った。
「ど・・・どいいう事ですか!なんともないなら・・・」
「まだ帰ってもらう訳にはいかないわ。せめて膣が形成されるまでね。」
「膣?」
悠真の心臓が激しく脈打った。
「残念だけどペニスはもうダメだったわ。衝撃で完全にちょん切れちゃってたから。」
「・・・え?」
悠真の時が止まった。
「ごめんね、奥まで咥えてたから♪」
女子大生が、両手を合わせて謝った。
股間に手をやる悠真。
そこには・・・何もなかった。
「よかったわね、これで心も体も『ゆまちゃん』になれるわね。」
菜穂子がニヤリと笑う。
悠真の絶叫が病院内に響いた。
終
「大丈夫?」
見ればベッドの傍には菜穂子に先程のOLに女子大生に女子高生。先程までかれを陵辱していた面々が顔を揃えていた。
「ひっ!」
一瞬の間に何が起こったのかを思い出し、悠真は悲鳴を上げた。
「心配しなくていいわよ、ここは私の知り合いの病院だから。」
菜穂子が笑う。
「あっ、あの・・・僕の・・・怪我は・・・・。」
加害者が目の前にいるため「怪我」という表現を使って悠真は尋ねた。
「大丈夫よ。なんともないわ。」
菜穂子の返事に悠真は安堵した。
「じゃ、じゃあもう家に帰ります。」
起き上がろうとした悠真を4人が押さえ込む。その時悠真は初めてピンクのハート柄の女性用のパジャマを着せられていることに気が付いた。
「な、何をするんですか!何も無いなら帰らせて下さい!」
悠真の叫びに4人は顔を見合わせた。
「もちろん、なんともないわよ。女の子としてはね。」
菜穂子の言葉の意味がわからず悠真は首を捻った。
「ど・・・どいいう事ですか!なんともないなら・・・」
「まだ帰ってもらう訳にはいかないわ。せめて膣が形成されるまでね。」
「膣?」
悠真の心臓が激しく脈打った。
「残念だけどペニスはもうダメだったわ。衝撃で完全にちょん切れちゃってたから。」
「・・・え?」
悠真の時が止まった。
「ごめんね、奥まで咥えてたから♪」
女子大生が、両手を合わせて謝った。
股間に手をやる悠真。
そこには・・・何もなかった。
「よかったわね、これで心も体も『ゆまちゃん』になれるわね。」
菜穂子がニヤリと笑う。
悠真の絶叫が病院内に響いた。
終
痴漢で目覚めた僕9
「あっ・・・やめてっ・・・」
菜穂子が悠真の足を抱き上げて持ち上げた。母親が幼い子供におしっこをさせる姿勢だ。
「まあ可愛いおちんちん・・・」
女子大生が悠真のペニスを弄ぶ。
「どれどれ、おまんこは処女かしら。」
OLが悠真のアナルに手を伸ばす。
「男でも胸感じるってホントかな?」
女子高生が悠真の乳首をつかんだ。
「ああぁ・・・だめっ・・・やめてっ・・・。」
悠真は抵抗するが、そのほかにも伸びてきた手が彼の手を拘束する。体中の性感帯を刺激された悠真は悪夢を見ながら夢精している様な気分だった。
「見てみて、この子包茎よ。可愛いっ!」
女子大生が言いながら悠真のペニスを口に含んだ。
「あ。。。ああっ・・・」
初めてのフェラチオの感触に悠真は悶える。
「なに勃たせてるんだよ、変態の癖して。」
女子高生がスカートを捲ると中には太いディルドー。族にペニスバンドとよばれる疑似ペニスが彼女の股間に装着されていた。
「さっきまで後輩の女の子を可愛がってたヤツだからちょっと太いけど我慢しな。」
女子高生は菜穂子と入れ替わると、ローションも塗らずに悠真のアナルにペニスバンドを突き立てた。
「ぎひぃーっ!!い、いたいっつ!ぬいて!ぬいてーっ!」
悠真の甲高い悲鳴が車内にこだまするが、無論助ける者などおらず、みな女の子に犯される女装少年という見せ物を楽しげに観察した。
「女に処女を奪われるなんて女装痴漢にはぴったりの刑だろう!」
「ひっ!ひっ!」
女子高生が持ち上げたままの悠真の身体を動かす。あまりの痛みに悠真は失神しそうだった。
「あらあら可哀想に、でもここは勃起したままね。」
女子大生は更に勃起した悠真のペニスを再度咥えた。後ろからの痛みと前の快感に悠真はもう訳がわからなくなり白目を剥いていた。
「ほらほら、寝るの早いわよ。」
「うぎゃーああっ!!」
菜穂子が悠真の乳首を抓って目を覚まさせたその時列車が急停止した。
車内の電気が消える。
続いてアナウンス。
「ただいま停電の為しばらく停車しております。」
一分後、灯りがつき列車は再び動き出した。その時
「きゃーっ!!」
OLの叫び声。
指さす先には悠真のペニスを咥えたまま口から血を流す女子大生の姿。
衝撃でペニスを噛んでしまったに違いない。
一方の悠真は・・・
ショックで失神していた。
菜穂子が悠真の足を抱き上げて持ち上げた。母親が幼い子供におしっこをさせる姿勢だ。
「まあ可愛いおちんちん・・・」
女子大生が悠真のペニスを弄ぶ。
「どれどれ、おまんこは処女かしら。」
OLが悠真のアナルに手を伸ばす。
「男でも胸感じるってホントかな?」
女子高生が悠真の乳首をつかんだ。
「ああぁ・・・だめっ・・・やめてっ・・・。」
悠真は抵抗するが、そのほかにも伸びてきた手が彼の手を拘束する。体中の性感帯を刺激された悠真は悪夢を見ながら夢精している様な気分だった。
「見てみて、この子包茎よ。可愛いっ!」
女子大生が言いながら悠真のペニスを口に含んだ。
「あ。。。ああっ・・・」
初めてのフェラチオの感触に悠真は悶える。
「なに勃たせてるんだよ、変態の癖して。」
女子高生がスカートを捲ると中には太いディルドー。族にペニスバンドとよばれる疑似ペニスが彼女の股間に装着されていた。
「さっきまで後輩の女の子を可愛がってたヤツだからちょっと太いけど我慢しな。」
女子高生は菜穂子と入れ替わると、ローションも塗らずに悠真のアナルにペニスバンドを突き立てた。
「ぎひぃーっ!!い、いたいっつ!ぬいて!ぬいてーっ!」
悠真の甲高い悲鳴が車内にこだまするが、無論助ける者などおらず、みな女の子に犯される女装少年という見せ物を楽しげに観察した。
「女に処女を奪われるなんて女装痴漢にはぴったりの刑だろう!」
「ひっ!ひっ!」
女子高生が持ち上げたままの悠真の身体を動かす。あまりの痛みに悠真は失神しそうだった。
「あらあら可哀想に、でもここは勃起したままね。」
女子大生は更に勃起した悠真のペニスを再度咥えた。後ろからの痛みと前の快感に悠真はもう訳がわからなくなり白目を剥いていた。
「ほらほら、寝るの早いわよ。」
「うぎゃーああっ!!」
菜穂子が悠真の乳首を抓って目を覚まさせたその時列車が急停止した。
車内の電気が消える。
続いてアナウンス。
「ただいま停電の為しばらく停車しております。」
一分後、灯りがつき列車は再び動き出した。その時
「きゃーっ!!」
OLの叫び声。
指さす先には悠真のペニスを咥えたまま口から血を流す女子大生の姿。
衝撃でペニスを噛んでしまったに違いない。
一方の悠真は・・・
ショックで失神していた。

![title1[1]](https://blog-imgs-74-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic28.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-58-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic27.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-58-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_picX1.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-49-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic26.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-49-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic25.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-61-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic24.jpg)
![title1[1]](https://blog-imgs-61-origin.2nt.com/s/e/x/sexchange/main_pic23.jpg)